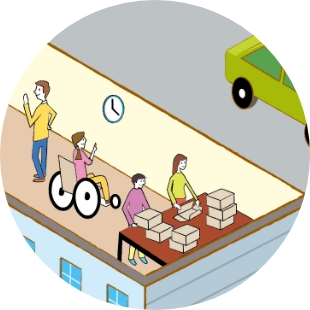目と手で「おしゃべり」
してみよう

笑顔と手話でお出迎え
ドアが開くと、おいしそうなにおい。一見よくあるカフェですが、店内でとびかうのは、元気なあいさつの声ではなく、やさしい手話と笑顔です。
東京・文京区にあるスープカフェ、「Social Cafe Sign with Me(ソーシャルカフェ サインウィズミー)」。ここではたらくスタッフは聴覚に障害がある、ろう者の人です。お店でつかっている言葉、公用語は手話なので、店内で話し声はほとんど聞こえません。
お店には、さまざまな工夫があります。たとえば、厨房(ちゅうぼう)のライト。ドアの開閉やよび出しボタンにあわせて点滅し、お客さんが来たことを知らせます。注文も、タッチパネルや筆談、またはメニューを「指差し」することでできるので、手話がわからなくてもだいじょうぶ。ろう者も聴者(耳が聞こえる人)も、みんながむりなくすごせる場所です。

「あたりまえ」を感じるということ
サインウィズミーでは、スタッフどうしのやりとりはかならず手話をつかうようにしています。そこにいるスタッフ全員が同時に情報を共有できるからです。
じぶんもろう者である代表の柳匡裕(やなぎ まさひろ)さんは、その場の状況を知ることがたいせつだと考えています。それは、逃げずにたちむかう力を育てるため。トラブルは、楽しいことではありません。けれど、それははたらくうえではあたりまえなこと。「怒っている手話」も、たくさん経験して、乗りこえなければいけません。
一方で、いっしょにはたらくスタッフみんなが手話でコミュニケーションできるおかげで、「まわりの話がわからない」という、さみしさを感じることはありません。わるいことも、いいことも、あたりまえに感じられるようになりました。
ちがいを知る、ちがいを楽しむ
ろう者にとっては、手話がとびかうにぎやかな場所ですが、聴者にとってはここちよい静かさを感じられる場所。お客さんは本を読んだり、勉強をしたり、静かに楽しんでいます。
「ろう者を知ってもらう場でありたい」と、柳さんは話します。実際に、取引先の業者さんが手話をおぼえてきてくれたり、メディアでとりあげられるようになったりして、てごたえを感じているそう。取材の日も、ろう者や手話のことについて調べている、大学生の方が訪れていました。
はじめての手話は、少しドキドキするかもしれません。けれど、笑顔で「ありがとう」と手話で言われたら、きっとあなたも手話で「ありがとう」を返したくなるはず。おいしいスープと手話でのコミュニケーションを、ぜひあじわいにきてください。
※本記事の内容は2022年12月時点のものです。