本文
出自と「痛み」が私を彩る -どちらでも「ない」から、どちらでも「ある」私へ
TOKYO人権 第98号(2023年5月31日発行)
インタビュー
Profile

石原 真衣(いしはら・まい)さん
1982年北海道生まれ。北海道大学アイヌ・先住民研究センター准教授(文化人類学)。母方の祖母がアイヌ、父方の祖母は屯田兵で会津藩の出自を持つマルチレイシャル※1。社会で不可視化され、沈黙する人びとに関する文化人類学的な研究を行っている。著書『<沈黙>の自伝的民族誌(オートエスノグラフィー)ーサイレント・アイヌの痛みと救済の物語』(北海道大学出版会)は大平正芳記念賞。
アイヌの出自を持つことを なぜ「沈黙」せねばならないのか

アイヌ※2の「ハーフ※3」である母と、和人(アイヌの出自を持たない多数派の日本人)の父の間に生まれた私は、幼いころはアイヌとかけ離れた世界で、平凡に生きていました。母から、母方の祖母がアイヌであることを聞かされたのは12歳のときでした。祖母はアイヌの文化や風習とは全く無縁に見えたので、あまりリアリティがなく、驚きました。それまでかぎかっこ付きの「日本人」として生きてきた私は、突然、居場所を奪われたような感覚を持ちました。
父は北方関連の専門書を扱う古書店を営み、特種な本の世界に生きているようなところがあり、いつも夢と希望にあふれ、私のことも常に100パーセント肯定してくれました。
私が周囲とは違っても臆することなく自分らしさを表現できるようになったのは、そんな父の影響が多大にあります。
一方で、母は私を心配するがゆえに、枠にはめようとしているように見えました。そこに母の出自にまつわる若いころの経験が影響していることには、大学院で研究を手掛けるまで気づくことができませんでした。母からは、自分がアイヌの出自を持つことを明かしてよいのは「北海道の歴史を正しく理解している人にだけだ」と諭されました。この言葉を聞いた当時の私は、「差別をされる対象だから隠さなければいけない」と理解していたように思います。そんな折、学校でアイヌを揶揄(やゆ)するような差別的な言動を見聞きすることもあり、とても居心地の悪い思いをしました。それもあって、母の言葉に従うかのように出自を明かすことなく「沈黙」したまま過ごしました。
アイヌの出自を隠しても、公言しても、居場所が見つからなかった
アイヌにも和人にもなれない居場所のない「痛み」
大学を卒業し社会人として働いた後、自分の出自について「沈黙」してきたことと、その「痛み」に向き合うため、研究者になる決心をし、28歳で北海道大学の大学院へ進学しました。
あるときは、アイヌの出自を持つと公言し、様々な人と交流してみました。しかし、アイヌ民族の衣装を着たりアイヌ語を勉強したりというような、アイヌ文化に身を置くことを頑なに拒絶していた私は、アイヌのコミュニティから、その態度を強く批判されました。
自分の祖先がアイヌ文化を捨てざるを得なかった背景にあるものを考えると、いかにも表面的なアイヌのイメージに安易に自分を寄せることは、私にはどうしてもできなかったのです。しかし、そのような態度はアイヌやその文化への裏切りのようにとらえられたようでした。
これは和人にもアイヌにも言えることですが、多くの人にとって「祖先にアイヌがいる」ことと、その人自身が「アイヌである」と自己認識しているかどうかの違いは、理解されていないような気がしていました。
当時、私の出自を知った知人から「(出自のことなんて)気にしないよ」と言われたのですが、私の中にはアイヌと和人、そのどちらの要素も存在しているはずなのに、「アイヌの祖先がいること」によって、「アイヌである」と一方的に決めつけられてしまうことに戸惑いを感じました。
「自然と共生する先住民から学ぼう」などと、アイヌ文化が褒め称えられても、私自身は、アイヌ文化について何も知らなかったし、自然の中でも暮らしていません。アイヌでも、和人でもない自分を意識したとき、どちらにも居場所のない私の姿はまるで透明で、誰にも見えていないような気がしました。
出自を公言する前に感じていた「沈黙」していたことへの「痛み」、そして公言した後に感じることになった、居心地の悪さと怒りの正体を解き明かすことが、私の研究テーマとなったのです。

自らの語りから見出した四世代にわたる「痛み」の物語
研究手法には、オートエスノグラフィー(自伝的民族誌/自己エスノグラフィー)と呼ばれる方法を選びました。この方法では、著者の個人的な経験を自伝的に記述することが研究の中心となります。
研究の対象は、私の曾祖母から始まり祖母と母、そして私自身です。四世代にわたるアイヌとその子孫の女性の生涯を記述していったのです。
曾祖母は、アイヌの成人女性としての証とされていたシヌイェという入れ墨を顔に施していました。バスに乗るときなど、和人がいるところでは、シヌイェを隠すために、白い三角巾で自分の顔を隠していたといいます。
8歳で和人の農家に奉公に出された祖母は、自分も和人と同じ生活水準で暮らすことを目指して勤勉に働きました。祖母がアイヌの生活様式を継承しなかったのは、アイヌであることを捨てて和人のように生きる方が幸せに生きていけると考えたためでした。
15歳のときから美容師として働きはじめ、その後様々な仕事をした母は、結婚してからは父と古書店を営み、娘である私への教育には出費を惜しみませんでした。
母は、若いころにアイヌの若者有志で刊行していた新聞の出版活動に携わっていました。そのことで警察から監視されていた時期もありました。そういった経験や、多数派と同じようにならなければいけないというマイノリティとしての経験があったために、子どものころの私が周りから逸脱した行動をとることを心配していました。
オートエスノグラフィーを書いてみて、曾祖母から祖母、母の時代までは、「痛み」を「痛み」として認識できる余裕など全くないほど過酷な状況にあったことや、そのような状況の中で次の世代が自分たちよりも少しでも良い暮らしができるようにと犠牲を払ってきた結果、今の自分が存在していることが分かったのでした。
研究を通して、アイヌやその子孫たちが、150年間にわたって置き去りにされた「痛み」を明らかにし、表現できたと思っています。
そして研究の過程で出会った海外の先住民やその子孫の中には、私と同じように、自分が多数派からも少数派からもこぼれ落ちてしまっていると感じている人が数多く存在することも分かりました。
研究が照らし出した「沈黙」を強いられる人たちの存在
博士論文としてまとめた成果を基に2020年に刊行した『〈沈黙〉の自伝的民族誌(オートエスノグラフィー)―サイレント・アイヌの痛みと救済の物語』は、多くの人に読まれ、増刷を重ね、賞も取りました。その結果、震災の被災者、公害病の被害者、同和地区出身者、在日コリアンなど、抑圧を受けている様々な当事者が「私も同じ思いをしている」と共感の声をくださり、つながりが得られました。
そこから、日本の社会の中にも、多数派からも少数派からも排除され、自分の居場所を見出すことができずにいる人が多くいる現状を知ることになりました。
アイヌの問題に限らず、「空気を読む」とか「立場をわきまえる」という言葉に象徴されるように、同調圧力が強く、和を乱さないことが求められる日本の社会では、マイノリティのみならず、「沈黙」を強いられ、社会から見えていない「透明人間」のような存在になっている人たちが多いのではないでしょうか。
ただ、私が研究者を志した時代と比較すれば、ここ15年ほどで日本の状況は大きく変わり、当時よりも人々の多様性が尊重されるようになりつつあると思います。アイヌの出自を持つことを自然に受け入れてくれる人も増えてきました。アイヌのコミュニティからも、着物を好んで着用するなど旧来のアイヌのイメージとは異なる私の振る舞いも、個性として認めてもらえている気がします。私に限っていえば、出自のことで孤独や「痛み」を感じることはなくなりました。どちらでも「ない」私から、どちらでも「ある」私へと変わってきたように思います。
マイノリティが人権を享受するには傍観者が変わることが必要
それでもいまだに、アイヌの出自を持つことが結婚差別などの対象となることがあります。その根底にあるのは被差別集団の血や出自を排除する日本国内におけるレイシズム(人種主義)です。
レイシズムやヘイトクライム※4を退け、マイノリティが「安全に暮らす」という人権を享受できるということは、社会全体が成熟し思いやり深く豊かであることを意味します。そうした人権を追求するために、マイノリティ集団内の多様性を殺すようなことも慎む必要があります。人間は本来一人ひとりがカラフルな存在です。
多数派の側にいる人々には、自分が差別に直接加担していない限り、自分の問題ではないと思えるかもしれません。しかし、近年の研究や議論が明らかにしているように、レイシズムやヘイトクライムがなくならない背景には、差別する側でもされる側でもない、「傍観者」の存在が非常に大きいです。マイノリティが当たり前の人権を享受できるようになるためには、市民の半数以上が差別やレイシズム、ヘイトクライムに「NO」と言えるようになる必要があります。
また、少数派の人々も、自分たちの活動や行為が、意図せずとも結果として一部の多数派に迎合することになっていないかを、常に問いかける必要があるでしょう。多数派が心地良いと感じることばかりを行い、それがあたりまえになってはいけない。
居心地の悪さを自覚したところに、個人の尊厳が損なわれている現実を理解するためのヒントがあると思うのです。


母イツ子さん作成のアイヌ衣装


『〈沈黙〉の自伝的民族誌
(オートエスノグラフィー)
― サイレント・アイヌの痛みと救済の物語』
石原 真衣 著(北海道大学出版会)
「居心地の悪さ」の自覚は、尊厳を取り戻すきっかけになる
「沈黙」しているあなたへ届けたいこと
「沈黙」するとは、隠さざるを得ない事情があったり、話したくても話す言葉が見つからなかったり、話したところでその話が通じなかったりすることだと思っています。そしてだからこそ、「沈黙」している人たちには、二つの守られるべき人権があると伝えたいと思っています。
一つは、「自分の言葉で語る権利」、もう一つは「語らない権利」です。
あなたの「痛み」はあなただけのもので、その「痛み」をあなたの言葉で語ることは、あなたが持っているはずの人権です。
そして同時に、なんらかの当事者性を持っていても、そのことについて、語らない権利も持っています。その権利を奪われることは、決してあってはならないことです。
私が伝えたいのは、どちらを選択したとしても、私は絶対にその選択を尊重したいということ。そしてもし、自分の言葉を見つけて自分の経験や「痛み」を語りたいと思ったときには、私にできることを一緒にしていきたいと考えています。
少しずつ、それぞれの「痛み」が癒される社会になっていきますように。そのために、これからも研究と活動を続けていきます。
※1 複数の人種の血筋を引いていること(小学館『デジタル大辞泉』より)。
※2アイヌ民族のこと。アイヌ民族は、古くより、主に北海道に先住し、独自の言語や文化を発展させながら生活していました。明治時代に入り、日本政府による同化政策が進むと、アイヌ語や独自の風習は失われ、その後もアイヌ民族はさまざまな面で抑圧されてきました。アイヌ民族にルーツを持つ人たちは、北海道はもとより、日本各地に存在しています。
※3 さまざまな歴史的状況の中で使われる用語としてかっこ書きで表記します。
※4 人種、宗教、肌の色、民族、性的指向、性別、障害などを理由とした憎悪あるいは偏見を動機とする犯罪(小学館『日本大百科全書』より)。
インタビュー 吉田 加奈子(東京都人権啓発センター専門員)
編集 杉浦 由佳
撮影(表紙・2~6ページ) 百代
石原さんのおすすめ書籍

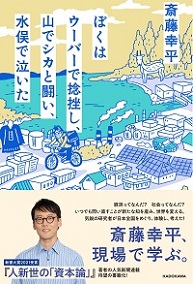
右/『ぼくはウーバーで捻挫し、山でシカと闘い、水俣で泣いた』斎藤 幸平 著(KADOKAWA)
左/『子どもたちがつくる町』村上 靖彦 著(世界思想社)
Copyright © Tokyo Metropolitan Human Rights Promotion Center. All rights reserved.




