本文
手話は一つの言語 「手話を『言語』として理解するには」
TOKYO人権 第97号(2023年2月28日発行)
JINKEN note/コラム
手話言語条例が導く多言語社会の日本
手話は一つの言語
「手話を『言語』として理解するには」
バイリンガル・バイカルチュラルという「ろう教育」の広がり 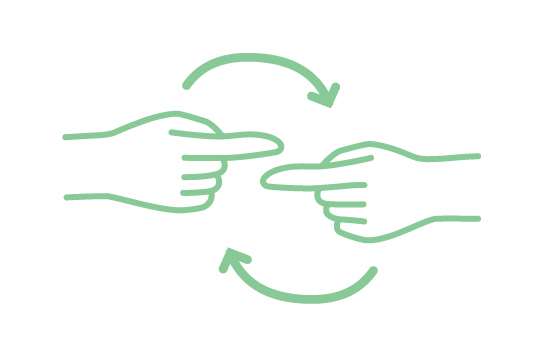
手話は一つの言語であるという理解が少しずつ広がっています。2011年に公布された改正障害者基本法に手話は言語であるということが明記されました。その後、現在までに34都道府県をはじめ464の自治体で手話言語条例が制定され※1、東京都では2022年9月に東京都手話言語条例が施行されました。
手話が言語であるという理解を広げるための自治体レベルでの取組が活発になっていますが、今回は、「手話が言語であるとはどういうことか」を考えるとともに、東京都手話言語条例の意義について、東京都聴覚障害者連盟の越智 大輔(おち・だいすけ)さんに聞きました。
手話は独立した言語体系を持つ一つの言語
手話は、手指の動きや表情を使って視覚的に表現する「見ることば」です。音声言語での会話が難しい人は、目で見てわかる方法で話をしますが、その一つが「手話」と言われます。
手話は独自の文法を持つ一つの言語で、例えば日本語で「山と海のどちらに行きたいですか」というところ、手話では「山/海/行き・たい/どちら(表情)」のように表現します。また、日本語に手話の単語を充てて表現する方法もあります。
音声言語である日本語は、その最小単位である音素の違いによって意味の違いを弁別しています。一方で、手話は手指で作る形だけではなく、動きの大小、スピード、位置関係、さらには表情などによって豊かな表現を生みだしているのです。このように手話は、日本語とは異なる独立した言語体系を持つ言語と言えます。
条例制定についての当事者の思い
過去の一時期、全国的にろう学校で口話指導が推奨されるなど、手話の使用については様々な制約を受けてきた歴史があります。東京都においては、2018年に東京都障害者差別解消条例※2が施行されて、
手話は言語であるということが明記されました。しかし、手話への理解を広げるためには、手話を幼児の頃から獲得するための環境整備や、手話を守るための学術研究の推進を可能にする、より踏み込んだ内容を包含した手話言語条例の制定が必要だと越智さんたちは考えていました。
越智さんは東京都手話言語条例の制定について、「手話は言語であるという理念が盛り込まれ、教育面において実効性のある事業と結びついている」と評価しています。条例には乳幼児からの手話教育に切れ目のない学習環境の整備や、手話の学習機会の提供、大学との連携といった条文が加えられ、手話を母語として獲得する環境整備が充実したものになることが期待されます。
聞こえる文化と聞こえない文化
「最近は、手話を言語として獲得してから日本語の読み書きを習得するという、二つの言語と文化を意味するバイリンガル・バイカルチュラルという『ろう教育』が広がっている」と越智さんは話します。聞こえる人と同じように社会で暮らすためには、手話だけでは難しいと言われていますが、日本語の学習において、ろう者にとって特に難しいのが読み書きです。越智さんは、「聞こえる社会の文化もきちんと身につけないと、日本語の読み書きを完全に習得できない」と説明した上で、「聞こえる人に手話が日本語と同じように言語であることを理解して、手話を必要とする聞こえない人がいるということに気付いてほしい」と訴えています。
聞こえる人とろう者がお互いの存在を相互に意識することで、手話は言語であるという理解が深まるのではないでしょうか。

越智 大輔さん(おち・だいすけ)
インタビュー・執筆 藤本 尊正(東京都人権啓発センター 専門員)
※1 一般財団法人全日本ろうあ連盟のホームページ(https://www.jfd.or.jp/sgh/joreimap)から引用。自治体数は2023年2月8日現在。
※2 正式名称は、「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」。
Copyright © Tokyo Metropolitan Human Rights Promotion Center. All rights reserved.




