本文
パートナーシップ宣誓制度とは
TOKYO人権 第96号(2022年11月30日発行)
特集
―みんなで一緒に歩くために 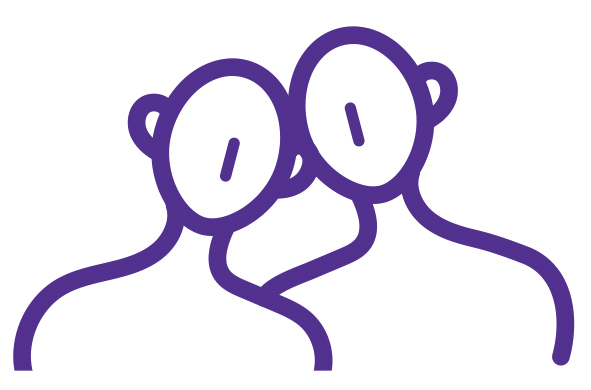
2022年11月1日、東京都は「東京都パートナーシップ宣誓制度(以下、宣誓制度)」の運用を開始しました。いわゆる「パートナーシップ制度」は、お互いを人生のパートナーであると宣誓または表明した性的マイノリティのカップルなどに対し、自治体が受理証明書や受領証などの公的な書類を交付する制度として、全国の自治体で導入が進んでいます。2015年に渋谷区と世田谷区で初めて制度がスタートして以来、現在全国で239自治体、都内では16自治体※1が導入しています(2022年10月現在)。これらの自治体の人口を合わせると、日本の総人口の5割以上をカバーし、制度を利用するカップルも3000組を超えています※2。本特集では、宣誓制度が導入された背景と、この制度によって変わることについて解説します。
制度設置の背景
人の生き方がそれぞれ違うように、性のあり方も人それぞれと言えます。日本国内における性的マイノリティの割合は、およそ5〜10%で、左利きの人たちと同程度の割合と言われています※3。その割合は、職場や学校などで「いない」と思われていても「見えなかった」だけで、実際には身近な人が該当するかもしれないことを物語っています。
パートナーシップに関する制度は、たくさんの「困った」からスタートしたと言われています。同性カップルなどは、法的保障の外に置かれていることから、例えば、パートナーと同居するときに賃貸住宅を借りることができなかった、病院の面会や手術の手続きで同意ができなかった、パートナーが亡くなった際にお葬式への参列をさせてもらえなかったなど、様々な面で困りごとがあります。東京都は、全国の自治体で初めて、届出から交付までオンラインで完結できる制度を導入しました。また、役所へ届出に行く際、意図せず他者に伝わることが気になって利用できないといった方に配慮した方法を採用しています。
制度導入でこう変わる
宣誓制度を導入することのメリットとして、住宅、医療、福祉など日常生活における様々な困りごとの軽減が挙げられます。具体的には、都営住宅への入居申込ができるなど、制度利用の新たな道が開かれることになります。先行して導入した自治体の制度利用者からは、パートナーが生命保険の受取人になれた、携帯電話の家族割が受けられた、パートナーの手術の際に家族として同意書に署名ができたといった報告もあり、今後、これまで以上に民間のサービス分野に波及することが期待できます。宣誓制度の意義について、東京都総務局の担当者は「この制度は、『「自分らしく」を、この街で。』をキーメッセージとし、人生のパートナーとして歩む性的マイノリティのお二人の暮らしやすい環境づくりにつなげるためのものです。制度導入をきっかけとして、多様な性への理解が深まり、誰もが自分らしく生き生きと活躍できる社会となることが大切であると考えています」と説明します。
宣誓制度は、婚姻制度とは異なり法律上の効果が生じないため、事業者などの制度への協力は任意となります。生活上の困りごとが軽減されるために、制度の意義などが広く認知され、証明書が活用されていくことが望まれます。
互いを尊重しながら一緒に歩く
東京都の宣誓制度導入について、自身も同性パートナーと10年以上暮らし、「東京都にパートナーシップ制度を求める会」の代表を務める山本(やまもと)そよかさんは、「勇気をもらえる」と話します。「自分の性のあり方を理由に、パートナーや家族に迷惑をかけているのではないかと思い、悩んだ経験があります。人との関わりをきちんと繋(つな)いで生きていけるというのは、生きる希望になります」とこれまでの歩みを振り返ります。また、多様性を認め合うという動きについて「性的マイノリティに限らず世の中には色んな少数者がいます。違いのある人たちが尊重し合いながら、多様性という一緒の方向を目指せる環境が進んで来たのでは」と話します。
誰もが自分らしく生き、安心して生活するためには、私たち一人ひとりがその人らしい生き方ができるよう後押しすることが大切です。多様性を認め合う風土を根付かせることは、様々な人権課題に直面している人たちにとっても意義深いと言えます。パートナーシップ宣誓制度は、自分らしく生きるすべての人を応援するための一つのカタチと、言えるのかもしれません。

山本 そよか(やまもと・そよか)さん
インタビュー・執筆 吉田 加奈子(東京都人権啓発センター専門員)
※1 東京都内では、10区(渋谷、世田谷、中野、豊島、江戸川、文京、港、足立、北、荒川)、6市(府中、小金井、国分寺、国立、多摩、武蔵野)がパートナーシップに関する制度を導入している。都道府県レベルでは9府県(茨城、大阪、群馬、佐賀、三重、青森、秋田、福岡、栃木)が導入している。
※2「 渋谷区・虹色ダイバーシティ 全国パートナーシップ制度共同調査(令和4年度第3回)」による。
※3「 出生時に判定された性別と性自認が一致し、かつ性的指向は異性」というパターンに当てはまらない人々は、性的マイノリティあるいはLGBTなどと呼ばれています。数字は、『「東京都パートナーシップ宣誓制度」をよりよく知るためのハンドブック』から引用。
Copyright © Tokyo Metropolitan Human Rights Promotion Center. All rights reserved.




