本文
「ほじょ犬」と一緒に生きている私たちをそのまま社会に受け入れてほしい
TOKYO人権 第95号(2022年8月31日発行)
Round-table Talk

Profile



写真左から
セア まり(せあ・まり)&盲導犬ベーチェル
網膜色素変性症(もうまくしきそへんせいしょう)による視覚障害がある。シャルル・ボネ症候群という幻視が現れる症状を併発。『見えない私の見える世界』を描く個展「景絵(ひかりえ)」を開くなどの活動をしている。
西澤 陽一郎(にしざわ・よういちろう)&介助犬ラッキー
25歳から車いす生活になり20年が経つ。介助犬と一緒に1人暮らしを再開。ラッキーと共に会社に勤務し多忙な日々を過ごす。休日はラッキーと出かけたり、旅行を楽しんだりしている。
松本 江理(まつもと・えり)&聴導犬チャンプ
聴覚障害で、23歳でほとんどの音を失う。聴導犬と暮らすようになり27年が経つ。子どもたちに向けて、補助犬や障害について伝える活動を積極的に行なっている。

橋爪 智子(はしづめ・ともこ)
NPO法人 日本補助犬情報センター事務局長。会社員時代にAAT(動物介在療法)に出合い、ボランティア活動をしながら国内外で学ぶ。身体障害者補助犬法の制定に準備段階から関わった。

「ほじょ犬マーク」
身体障害者補助犬法の啓発のためのマークです。この法律では、公共の施設や交通機関、デパートやスーパー、ホテル、飲食店などの民間施設は、身体障害のある人が補助犬を同伴するのを受け入れる義務があることを定めています。
座談会メンバー
コーディネート(司会)
(1)橋爪 智子さん
(2)セア まりさん&盲導犬ベーチェル
(3)西澤 陽一郎さん&介助犬ラッキー
(4)松本 江理さん&聴導犬チャンプ
 (1)
(1)  (2)
(2)
 (3)
(3) 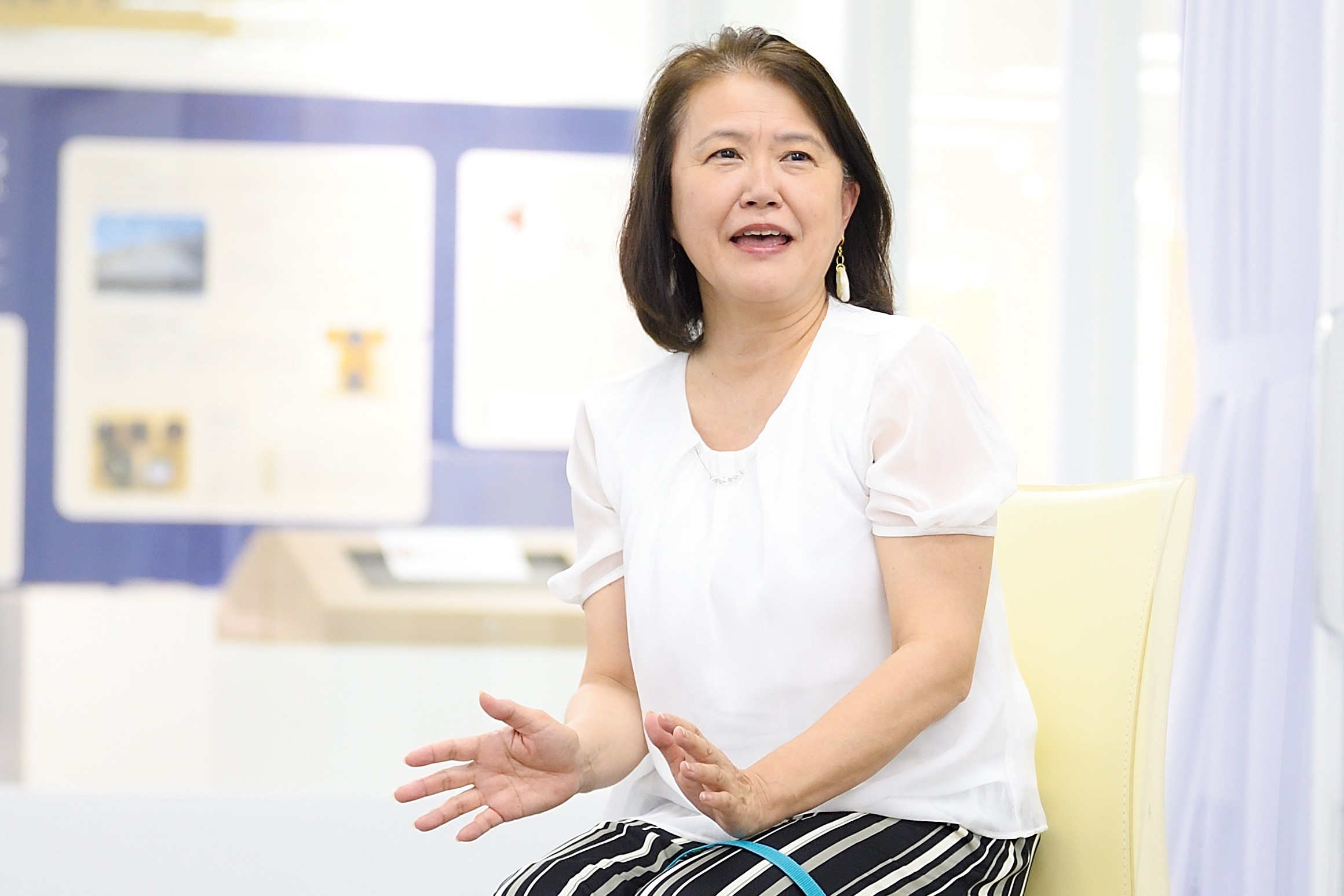 (4)
(4)
補助(ほじょ)犬は身体障害者をサポートするパートナーとして長い歴史を持っています。2002年10月に「身体障害者補助犬法」が施行され20年が経過しました。当時は不特定多数が利用する施設への補助犬同伴受け入れが義務化されたことが、マスコミにも取り上げられ話題になりました。現在も、補助犬への誤解から、いまだ同伴受け入れ拒否に遭うことも少なくありません。そこで、盲導犬・介助犬・聴導犬のユーザーに、それぞれの日常や心情について語り合っていただきました。
補助犬と暮らすようになったきっかけ
橋爪 自己紹介も兼ねて、ご自身の障害と、今取り組んでいることなどについて、お話しいただけますか。
セア 私は進行性の網膜色素変性症(もうまくしきそへんせいしょう)による視覚障害があって、今いるこの部屋でも何となく光を感じられる、というくらいです。20年前に始めたスキューバダイビングにはまり、10年ほど前からは競技のフリーダイビングにのめりこんでいます。5月には神戸で「シャルル・ボネ症候群」の世界を描いた絵画の個展を開きました。
西澤 色々な活動をされていますよね。私は25歳のときに車いす生活になって「もう何もできなくなってしまった」と悲観して、家にこもって暮らしていたんです。でも介助犬と暮らすようになってから気軽に外に出られるようになって、週末は旅行に行ったり、介助犬と一緒にハワイにも行ったりしました。
松本 私は後天性の聴覚障害なんですが、23歳でほとんど聞こえなくなって、その後聴導犬と暮らすようになって27年目です。手芸やアクセサリーを作ったり、聴導犬チャンプの様子をSNSに投稿したりして楽しんでいます。
橋爪 みなさん、いろいろと活動的ですね。補助犬を共に生きるパートナーとしながらの生活だと思いますが、いつどのようなきっかけで補助犬を迎えることになったのですか。
セア 盲導犬と暮らし始めたのは15年ほど前です。昔から動物愛護の運動をしていて、盲導犬は厳しく訓練されて働かされていてかわいそうだと思っていたから、「私は絶対使わない!」と心に決めていたんです。でも実は盲導犬になる犬は、愛情をたっぷり与えられて育っていることを知って、「それなら私も!」と。もともと動物は好きですから。
西澤 私が最初の介助犬と暮らし始めたのは14年くらい前です。当時は、実家で両親に助けてもらいながら暮らしていました。でも本当は自立したかったんです。あるとき、街中で介助犬を連れている人を見かけて、「そうだ、介助犬がいれば自立できるかもしれない」と思って、その人に声をかけて、あれこれ話を聞いたんです。それがきっかけでしたね。
松本 障害のことを重く考えて、できないことばかり考えてしまうときが私にもありました。でも、補助犬という選択肢を知って変わったんです。私が聴導犬と暮らし始めたのはかなり昔のことで、きっかけは結婚でした。独身のときは実家で家族に助けてもらいながら生活していたので、結婚して実家を出た後はどうすればいいんだろうと途方に暮れていました。そんなとき、あるイベントで聴導犬のデモンストレーションを見て、こんな犬がいたら私も結婚してもやっていけると思って。
橋爪 補助犬によって可能性が広がり、生き方そのものも変わってくるのですね。具体的には、補助犬はどのようにみなさんをサポートしてくれるのでしょうか。
松本 音が聞こえないと、いつ誰が来るか、いつお湯が沸くか、いつ赤ちゃんが泣くか、音が鳴っていないときにも、ずっと気を張っていなきゃいけないんです。聴導犬がいれば、そういう音を全部教えてくれるので、音のことは忘れて安心して好きなことをしていられます。たとえば赤ちゃんのことを常に見ていなくても、私が眠りこんじゃっても、赤ちゃんが泣きだせば、聴導犬が教えてくれます。
西澤 そうそう。思いがけないメリットがあるのです。たとえば介助犬ラッキーを連れて外出するようになってから、近所の人とよく話すようになりました。東日本大震災のときも近所の人たちが、「犬を連れている車いすの人は大丈夫かな」と安否を気にかけてくれて。もちろん、車いすを引っ張ってくれたり、物を落としたら拾ってくれたり、介助犬としての仕事でも助けられていますよ。
橋爪 落とした物を拾ってもらうとき、誰かにお願いしたときと、ラッキーがしてくれたときでは、何か違いがありますか。
西澤 介助犬とは一心同体のような感じで、ラッキーがしてくれたことは自分でやったような感覚なんです。遠慮もないですし、気持ち的に大きな違いがありますね。それが自信にも繋(つな)がっているのか、両親からも「性格がとても明るくなって、安心した」と言われました。

介助犬は物を拾ったり、車いすに付属したワイヤーやスカーフを使って段差をアシストしたりする

介助犬ラッキーが、落としてしまった鍵を拾う
無償の愛情を体中で表現した盲導犬フリルの「大勝利」
セア 補助犬が心を明るくしてくれるんですよね。盲導犬と一緒にいると笑顔になって顔が上がるってみんな言っています。私も、以前は足元を探りながら歩いていたのが、前を向いて背筋をピンと伸ばして歩けるようになりましたしね。ただ、世の中にはまだまだ誤解もあって、ガイドさんと盲導犬を連れて歩いていたら、「ずいぶんいい身分じゃないか」と嫌味を言われたことがあって、ショックを受けました。
橋爪 セアさんは、頭の中で地図を思い描ける場所なら盲導犬とペアで歩けるけれど、初めて行く場所にはガイドさんが必要になる。そのことが、その人には分からなかったのでしょうね。
セア こんなこともありました。盲導犬を連れて募金活動に参加したら、男性が「犬が電車に乗るだのレストランに行くだの、とんでもない!」と怒鳴って、カバンを振り回して暴れだしたんです。盲導犬協会の人がとりなそうとしても「犬は大嫌いだ!」と取り合ってくれなくて。そのとき、以前一緒に暮らしていた盲導犬のフリルが、その人の前にちょこんと座って、ぶんぶん尻尾を振って体中で愛情を示し始めたんです。その人が「犬は嫌いだって言ってるだろ!」と怒鳴っても、ずっと尻尾を振っていて。そのうちに、その人は「負けた」とつぶやいて去っていったんです。なんだかすごく感動して、フリルから人との接し方を教わったような気がしました。
橋爪 補助犬になる犬たちは、小さいうちから愛情いっぱいに育てられているので、人間に対する信頼感が違うのでしょうね。大好きなお父さん、お母さんに褒められたい子どものような気持ちで、パートナーに対する無償の愛を感じます。

盲導犬ベーチェルは、歩行中の曲がり角や段差、障害物を教えてくれる

歩行中、聴導犬チャンプが後ろから自転車が来ていることを教えてくれる
外出先で気づいた聴導犬の意外な役割
松本 西澤さんがおっしゃっていたように、補助犬がいることで、間接的に助けられていることが私にもあります。私の場合、聞こえなくても、一人で移動はできるのですが、街にいるとき周囲の人には私の障害が見えません。だから、何か異常な事態を告げるアナウンスが流れていても、周りの人は私にもそれが聞こえていると思うんです。でも、実際には聞こえないので、一人だけ取り残されてしまう。それが「聴導犬」と書かれたケープをまとった犬と一緒にいると、私が聞こえない人だと分かるので、気づいた人に声をかけてもらえるんです。
例えばバスで初めての場所に行くとき、降りるまでずーっと窓の外やバス停の表示を必死の形相で確認することになるのですが(笑)、聴導犬がいると、誰かが声をかけて助けてくれるんです。実際に何度も助けられました。
「補助犬法」はできたけれど、まだまだ誤解や偏見は多い
西澤 でも、補助犬は強制的に大変な仕事をさせられてかわいそうだと思い込んでいる人たちもけっこういて。突然やってきて「犬に仕事をさせるなんてかわいそうじゃないか」と言い放って、こちらが反論する暇(ひま)も与えず去っていく人もいました。もうなんともいえない悲しい気持ちになるんですが、介助犬と目が合うとね、ニコニコして尻尾をぶんぶん振って「一緒に歩くの楽しいね!」と言ってくれているんです。自分は介助犬と一緒にいるから頑張れるし、幸せでいられるんだな、とつくづく感じます。
橋爪 補助犬のことをかわいそうな犬だと思っている人もいれば、完全無欠のスーパードッグだからいつも模範的(もはんてき)な姿を見せるべきだと思い込んでいる人がいたり、かと思えば、犬だからところかまわず吠(ほ)えたり粗相(そそう)をしたりするのではないか、という偏見があって入店を拒否するお店もあります。それぞれの思い込みで、補助犬に対してまちまちな印象が混在している社会で過ごすのは、本当に大変ですよね。多くの人に補助犬のことを正しく知ってもらえる機会をつくっていきたいです。
「補助犬法」が制定されて20年になります。もともとは介助犬のための法律として制定されようとしていたのを、松本さんたちの尽力があって、聴導犬と盲導犬も対象に含まれたのですよね。松本さんはこの法律が制定される前から聴導犬と生活されていますが、法律ができる前とできた後で何が変わりましたか。
松本 補助犬法ができるまでは、盲導犬以外の補助犬には、はっきりした基準がありませんでした。法律の制定後は、定められた基準によって認定された犬たちだけが盲導犬・介助犬・聴導犬と名乗れることになりました。そのために、いろいろな責任も生まれたのですが、半面、お墨付きを得ていることは後ろ盾にもなっています。とはいえ、今でもタクシーが停まってくれなかったり、レストランの予約を断られたりすることがあって、法律ができたらそれで180度変わるわけではありませんでした。

盲導犬は体にハーネスという白い胴輪をつけ、動きをユーザーに伝えている
補助犬と一緒にいる私たちが自然に受け入れられる社会を


セットしたタイマー(左写真)が鳴ると、跳び上がって知らせる(右写真)聴導犬チャンプ
セア 何も特別なことを求めているわけじゃなくて、ただ傍ら(かたわ)に盲導犬がいるということを自然に受け入れてほしいんです。例えばお店に入ろうとしても、拒絶されることもあるし、反対に受け入れてくれたお店で不自然に気を遣(つか)われて居心地が悪くなったり。
西澤 私は介助犬と一緒に一般企業に勤めているんですが、補助犬を連れて一般企業に勤めている人はまだまだ少ないと思います。補助犬の必要性を分かってもらうまでには、高い壁があることを、身をもって実感しました。今では、ラッキーは職場でアイドルのような存在になっていますけどね(笑)。補助犬の働きぶりを実際に見てもらえれば受け入れてくれる職場は多いはずなんですが。
松本 「障害者の人権問題」として堅(かた)く考えてしまう前に、障害者と補助犬の関係について知ってもらう機会をもっと増やして、補助犬を通じての社会参加を受け入れられる社会になるといいですね。
セア 障害のあるなしに関わらず、私たちだって、行きたいところに行って、やりたいことをしたい。それができないのは、障害のせいではなくて「障害のない人中心の社会」のせいだと思うんです。
橋爪 障害イコール「何もできない人」という見方をやめて、あたりまえに同じ仲間なんだということを認識してもらうことからのスタートだと感じます。そのために、補助犬やみなさんのことについて、もっと知ってもらう活動をしていきたいですね。
企画 田村 鮎美(東京都人権啓発センター 専門員)
編集 杉浦 由佳
撮影(表紙・2〜6ページ) ウエストゲート 里永 愛
協力 NPO法人 日本補助犬情報センター
Copyright © Tokyo Metropolitan Human Rights Promotion Center. All rights reserved.




