本文
3つの事例で学ぶ、人権と映画
TOKYO人権 第82号(2019年7月31日発行)
特集
3つの事例で学ぶ、人権と映画
映画には、記録(アーカイブ)や宣伝(プロパガンダ)、娯楽(エンタテイメント) の機能とともに、教育的な側面があります。啓発と映画というのは、じつは相性がよく、人権について深く掘り下げたものや、人権問題を学べる作品も数多くあります。今回の特集では、映画を通じて人権を学ぶためのアプローチを、3つの事例に即して考えてみます。
作品から学ぶ、マイノリティの権利と連帯『ハーヴェイ・ミルク』
【クイズ】
自分が性的少数者等であるということを表明する「カミングアウト(coming out)」がこの様な表現になったのはなぜ?
答えはページ下にあります。
1970年代の米国サンフランシスコで、ゲイであることを公言(カミングアウト)して政治活動を行い、市政執行委員に当選したハーヴェイ・ミルクの活動と暗殺を記録したドキュメンタリー映画です。70年代のサンフランシスコはゲイ解放運動が大きな盛り上がりを見せていた時期で、各地から多くの当事者が集まり、とりわけハーヴェイ・ミルクが活動拠点を置いていたカストロ通りは、アメリカ屈指のゲイコミュニティが成立していました。ミルクはそこで政治活動を始め、多くのマイノリティから支持を集めました。そしてゲイを公言している人物としては初めて、市政執行委員という公職に就任したのです。
映画はその冒頭で、サンフランシスコ市長とハーヴェイ・ミルクが、同僚の市政執行委員D・ホワイトによって市庁舎内で射殺されたと発表されるシーンから始まっています。そのことからも分かるとおり、ミルクらの活動は一方では強い批判にさらされ、さらにゲイに対する根強い偏見や差別の中で反対派との政治的な争いを強いられたものだったのです。選挙によって公職に就いてから、わずか一年足らずでの暗殺でした。
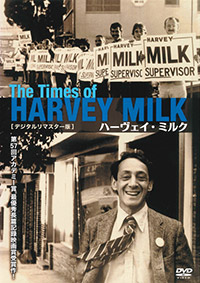
『ハーヴェイ・ミルク』DVD ⓒパンドラ
原題 The Times of Harvey Milk
1984年アメリカ
映画の中でミルクはインタビューに答えて、自らが公職に就いた意義を次のように話します。「信じられない(インクレディブル!)特権階級…白人や権力者、ノン・ゲイ―、大金持ちも私を無視できない。すごい立場ですよ」(字幕より)。また彼の支持者であり協力者である労働組合の幹部は、「彼は立場をはっきりさせていた。少数派としてのゲイのために、そして他の少数派のために」と評価しています。ミルクらの活動は、マイノリティが、その権利獲得のために他のマイノリティ、例えば性的少数者、障害者、移民などさまざまな人々と連帯することが可能であり、大切であることを教えてくれます。
この映画を日本で公開・配給した中野理惠さん(株式会社パンドラ)は、作品を「人間の尊厳を描いた映画」として位置づけます。そして「その存在が見えないものであるように扱われていた人々、すなわちマイノリティは、まずは声をあげ、その存在を主張するところから始めなければならなかったのです。公開にあたって、これは民主主義のお手本のような映画だという評価をいただきました」(中野さん)と語ります。
1988年9月に日本で初公開されてからすでに30年以上が経過したこの作品は、ドキュメンタリー映画史上にその足跡を残す作品として評価されるとともに、今でも各地で上映会が企画されているロングセラーであり、そのこと自体が今もって性的少数者への社会的偏見がなくなっておらず、その理解促進についての啓発が必要であり続けていることを証明するものとなっているのです。
「31年前に試写を見てもらうために呼びかけたメディアの人たちの多くは、当初は偏見を含んだ否定的な反応を示しました。中には「オカマの猟奇殺人」(!)とまで表現した方もいたくらいです。しかし試写の後には、これは多くの人が観るべき作品だと一転して評価してくれました」(中野さん)。はからずもこの映画が、人権について学ぶための優れた素材であることを示していると言えるでしょう。
映画祭に参加してみる。ワンズ・アイズ映画祭vol.1「ともに生きぬく」
4月のある晴れた日曜日の朝、JR中央線の武蔵小金井駅で下車し、南口駅前にある小金井市宮地楽器ホールへ向かいました。目的は、ここで行われる映画祭に参加すること。「ワンズ・アイズ映画祭」は今回初めて開催された、できたての映画祭です。「ともに生きぬく」をテーマに4本の作品が上映されました。
上映されたのは、大西暢夫監督の「家族の軌跡〜3.11の記憶から〜」(2016年)のほか、『被ばく牛と生きる』(松原保監督・2017年)『願いと揺らぎ』(我妻和樹監督・2017年)そして塚本晋也監督の『KOTOKO』(2011年)というラインナップで、中心となっていたのは東日本大震災後の様々な困難な状況の中で、家族、地域、生きものたちと、ともに生き抜こうとする人たちを描いた複数の作品でした。
大切な人、生活や働く場等を失うなど、被災者は大きな被害を受けます。回復のために必要なのは、避難生活における様々な配慮や、物質面および心理面での支援、そして回復にかかる時間です。しかし、一方で時間の経過により記憶の風化が生じやすく、ときに被災者は社会から取り残されたような感覚におちいることがあります。この映画祭で上映された作品の作り手たちは、それぞれのスタンスで被災者や被災地の記憶と共にあろうとする強い意思を持ち、各作品にはそうした思いが込められていました。
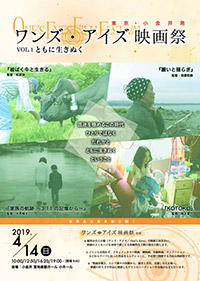
ⓒワンズ・アイズ映画祭実行委員会
実行委員の一人、映画監督の纐纈[はなぶさ]あやさんは次のように語ります。
「被災した方たちにとって、この8年がどのような月日だったのかは、到底伺い知ることはできません。また、カメラの前で恐怖や喪失、混乱の記憶を語ってもらうことは、語る方も、聞く方も、どれだけの痛みを伴ったかと思います。それでも今回上映した作品の製作者の方々にとって、これは自分たちがしなくてはいけないこと、という止むに止まれぬ思いがあったのだと思います」。
参加した方からは「単独で観るより、それぞれの作品が自分の中で有機的にからまって、より開かれた視野でいのちや生きることについて考えるヒントをもらえました」という感想が寄せられています。ワンズ・アイズ(One’s Eyes)、すなわち観客が自らの眼で映画と向き合えるような、上映の場を目指した取り組みは、ひとまず成功したと言えるでしょう。
ところで、小金井市には現在常設の映画館がなく、市民有志による「小金井に映画館をつくろうプロジェクト」が以前から活動していて、今回の映画祭はその一環として行われたものだそうです。地域で暮らし、地域を愛する人々によって企画され、実現したこの小さな映画祭が、次回以降どのように発展していくのか。今後の展開が注目されます。
映像ライブラリーを活用する
多くの公共図書館は視聴覚資料として映画や映像作品を備えています。また博物館や美術館等の文化施設には、付属する機能として映像ライブラリーなどを設けているところもあり、無料で映画作品を視聴できる施設というのは、意外に数多く存在します。さらに、映画や放送番組を専門的に収集し、公開している施設もあって、それらは利用料がかかる場合もありますが、活用が可能です。
そうした中、人権のジャンルに特化した映像ライブラリーとして、東京都人権プラザ(港区芝)の図書資料室をご紹介します。図書資料室にはビデオライブラリーが置かれ、700タイトルの啓発ビデオやDVDなどを備え、視聴と貸し出しを行っています。施設内には視聴のための専用のコーナーが設けられていて、配架された棚から自分で作品をピックアップして、視聴することができます。ちなみに、この特集記事で取り上げた『ハーヴェイ・ミルク』も、5頁のコラム記事で紹介されている『奈緒ちゃん』も、このライブラリーで観ることができます。
貸し出しを受けることができるのは、東京都内に居住、通勤・通学されている方。DVD等の貸出点数は1人5点までで、貸出期間は1週間以内です。
インタビュー・編集/坂井 新二(東京都人権啓発センター専門員)
クイズの答え
coming out of the closet(押し入れの中から出てくる)の短縮形として「coming out」が使われるようになりました。隠していたことを公言する比喩表現です。
人権プラザからのメッセージ

どうぞお気軽にお立ち寄りいただいて、様々な映画作品を楽しみながら、人権について学ぶきっかけにしてみてください。また人権学習や研修のための素材をお探しの場合は、図書資料室のカウンターへご相談ください。最適の作品を選ぶためのお手伝いをいたします。みなさまのご来場を心よりお待ち申し上げます。
Copyright © Tokyo Metropolitan Human Rights Promotion Center. All rights reserved.




