本文
「目に見えない世界」の魅力を伝えたい
TOKYO人権 第80号(2018年12月20日発行)
インタビュー
「目に見えない世界」の魅力を伝えたい
全盲の文化人類学者が世界を「さわる」
全国の博物館や美術館で、「さわる」ことをテーマにした展覧会をプロデュースする広瀬浩二郎さん。視覚障害者に美術作品の鑑賞を楽しんでもらうと同時に、目が見える人にも「さわる」ことを通して新しい発見や感動を提供することを目指しています。「さわる」ことの魅力とは何か。見えない世界とはどのようなものなのか。全盲の広瀬さんがどのように生き、文化人類学者としてどのようなことに取り組んでいるのかをお聞きしました。
PROFILE

広瀬(ひろせ ) 浩二郎(こうじろう )
国立民族学博物館 グローバル現象研究部 准教授
1967年、東京生まれ。13歳で失明。筑波大学附属盲学校から京都大学に進学。1993年、京都大学大学院文学研究科修士課程修了。1995年、カリフォルニア大学バークレー校留学。2000年、京都大学大学院にて文学博士号取得。2001年より国立民族学博物館に勤務。2008年、同館准教授。専門分野は日本宗教史・民俗学、触文化論。「さわる」ことをテーマとした各種イベントを全国で企画・実施する。著書に『目に見えない世界を歩く』(平凡社)、編著書に『ひとが優しい博物館』(青弓社)など多数。
国立民族学博物館<外部リンク>
どのような子ども時代を過ごしましたか。

僕の目の病気が分かったのは1歳半のときです。まず左目が見えなくなり、弱視の右目もだんだん視力が下がっていきました。それでも、小学生のときはまだ0.05前後の視力があったので、日常生活にそれほど不自由はなく、地域の小学校に通っていました。
ところが小学5~6年くらいから、さらに視力が下がって教科書の文字が読めなくなり、体育の球技では、ボールが見えなくなりました。
そこで、中学校から筑波大学附属の盲学校に通うことになりました。しかし、当時の僕は盲学校に「暗くて後ろ向きな場所」とのイメージを持っていました。それまで地域の小学校で目が見える友達と一緒に過ごしてきた自負もあり、子どもながらに複雑な心境で入学式を迎えたことをよく覚えています。
その後、13歳で完全に失明したこともあり、高校卒業までの6年間を盲学校で過ごすことになるのですが、結論から言うと、とてもよい年月だったと思っています。周りの友達と話すのは、野球や相撲、アイドルのことなど、小学校の同級生とまったく同じで、すぐになじめましたし、視覚以外の感覚を使うことをじっくり身に付けられたこともよかったですね。点字での学習をはじめ、美術では粘土など触覚を生かした制作をしたり、体育では水泳などあまり視覚に頼らなくてもできる競技をしたり。視覚障害があっても学べることやできることはたくさんあると実感し、自分に自信を持つと同時に、友達との競争も楽しめました。最近はインクルーシブ教育が導入され、盲学校に賛否両論はありますが、僕は人生のある期間、同じ個性を持った者同士で切磋琢磨することは大切だと感じています。
琵琶法師や 瞽女(ごぜ) を研究テーマとしたのはなぜでしょうか。
高校では2年生くらいから進路指導が始まりました。僕は中学生のころから司馬遼太郎の歴史小説を読んでいて歴史が好きだったので、大学に進学して日本史を学ぼうと考えました。しかし、高校の先生はあまり賛成してくれませんでしたね。視覚障害者にとって古文書を解読するのは大変で、ボランティアに頼むとしても、専門的な知識がないと読めないからです。実際、いくつかの大学を受験する際、「視覚障害者に日本史学科は難しい」と受験を断られたこともあります。また、ある大学からは「過去に視覚障害者を受け入れた前例がない」との理由だけで受験を拒否されたこともありました。
僕はそれまで、強がりでもやせ我慢でもなく、目が見えないことはそんなに大したことではないと思っていました。しかし、自分の感覚と社会の認識にはズレがあることを、大学受験で初めて実感しました。
それでも、一浪して京都大学に進学し、僕は日本史学科で障害者の歴史について研究を始めました。昔は医学が発達していませんから、障害者の数は今より多かったと思うのですが、教科書にはほとんど登場しません。これは、そもそも教科書を書いている人たちが障害者と接する機会が少なかったために、障害者の存在を忘れているからではないでしょうか。その忘れられた歴史を掘り起こすのは、当事者である僕たちがするべきだと考えていました。
そうした中で、出会ったのが「琵琶法師(注1)」です。僕が大学生だったころは、まだ九州に琵琶法師の方たちが何人か残っていたので、直接お話を聞くこともできました。時代は全く違うとしても、自分と同じように目の見えない人たちが、平安中期からさまざまな物語を語り、職業集団として生き抜いてきたことに勇気づけられました。
大学院では、もう少し範囲を広げ、イタコ(注2)や瞽女(注3)に関する研究も行い、そうした方々の拠点であった東北や新潟にも足を運び、聞き取り調査を行いました。
受験や就職活動のなかで痛感したことは、社会は視覚障害者の“できないこと”ばかり数えて、あげつらうということです。しかし、琵琶法師や瞽女といった人々は、見えない世界で“できること”を見つけて個性を発揮していた人々でした。視覚障害者を「視覚を使えない人」から「視覚を使わない人」と見方を変えてみる必要があると考え始めました。
国立民族学博物館でのお仕事について教えてください。
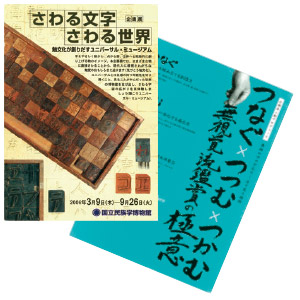
実を言うと、僕は失明してからというもの、博物館にあまりいい思い出がありませんでした。大抵の博物館は資料保存のために照明を暗くし、展示物をガラスケースに入れているので、視覚障害者は楽しめないのです。今でこそ、全国の博物館では視覚障害者向けにさまざまな取り組みを行っていますが、僕が盲学校に通っているころは、ほとんどありませんでしたから。
当時はそれほど深くとらえていませんでしたが、就職後、博物館について改めて考えてみると、「博物館は視覚障害者から一番縁遠い場所だ」と思いました。そして同時に、「僕も博物館を楽しみたい」との思いが湧き上がってきたのです。僕が楽しめれば、きっと多くの視覚障害者も楽しめるのではないかとも思いました。
そこで最初に取り組んだのは、点字パンフレットの作成や、広報誌『月刊みんぱく』のカセットテープ版の作成です。こちらはその後CD版になり、現在はホームページで音訳データを提供する仕組みを構築しているところです。
そして2006年、初めて視覚障害者に開かれた展覧会として「さわる文字 さわる世界」と題した企画展を行いました。京都と東京の盲学校の資料などを展示し、直接さわっていただくことに重点を置いたものです。これが予想以上に好評をいただき、その後も関連したワークショップの依頼をいただくようになりました。
2回目の企画展は2009年で、点字考案者のルイ・ブライユ生誕200年記念として「点天展」と題した展覧会を行いました。このころから、僕の仕事は博物館の展覧会を通して、社会にメッセージを届けることが中心になっていきましたね。2012年には、当館に常設の展示コーナーを設け、いつでも展示資料にさわる体験ができるようになりました。
「さわる」展覧会を通して「みえる」こととは。

この展示コーナーは、当初から、視覚障害者だけでなく、目が見える人たちにも何かメッセージを届けるものにしたいと考えていました。そこで、「目が見える人は視覚に頼るため、意外と触覚を使っていない」との視点から、「目が見える人もさわろう。日常生活の中にさわることを取り戻そう」と呼びかけました。
結果的には、「さわって楽しかった」、「見るだけでは気づけないことに気づけた」などの感想をいただき、それなりの手ごたえはありました。しかし、「見えない人がさわるのと、見える人がさわるのとでは、根本的に違う」と感じたのも事実です。いいか悪いかは別として、目が見える人にとって、さわることはあくまでも視覚を補助する意味合いが強いということです。
そこで、もっと触覚に特化した体験ができるようにとプロデュースを始めたのが「無視覚流鑑賞の極意」と題した展覧会です。初回は2016年に兵庫県立美術館で開催しました。来館者には入口でアイマスクをしてもらい、最初から視覚を使わない状態で彫刻作品にさわってもらうという企画です。果たして受け入れてもらえるだろうかと不安でしたが、来館者には主旨が伝わったようで、さわることをより深めることができたかなと感じています。
そして、この企画展を通してもう一つ伝えたいのが「さわるマナー」についてです。露出展示をすると、多くの場合、「さわってもいいなら、遊んでもいいし、壊してもいい」と思われがちで、特に子どもの遠足などでは破損事故が起きることも少なくありません。では、どうすれば優しく丁寧にさわってもらえるのか。僕としては、さわりながら、その展示物を作った人や使った人の思い、今日まで伝えられてきた歴史など“物の背後にあるもの”を追体験する気持ちが大切だと考えています。また、そうした気持ちがあると、より深い感動を得ることにもつながると思うのです。
実際、2017年の国民文化祭の関連イベントの中で、僕自身が奈良県文化会館で興福寺の「 銅造仏頭(どうぞうぶっとう) 」の精巧なレプリカをさわったときのことです。僕は歴史が好きなので、その仏頭が国宝で、頭部だけが焼け残った歴史的背景も知っていました。しかし、素材も見た目も忠実に作られたそのレプリカを、自分の手で確認できたことに、まず大きな喜びを感じました。
そして忘れられないのが、火災に遭い、欠けてギザギザになった左耳にさわったときです。「これは痛いだろうな」と、まるで自分のことのように感じました。冷静に考えれば、その仏頭は本物そっくりとはいえレプリカですし、実際に僕の耳が切られたわけでもないのでおかしな話です。でも、さわることで仏頭と自分がダイレクトにつながるような感覚を味わえたのだと思います。こうした感動を、より多くの人に体感していただくためにも、優しく丁寧にさわることを根付かせていけたらと思っています。
最後に、障害者の人権を考える際に大切なことは何でしょうか。
僕は、障害者が健常者と同じことができるように保障することはもちろん大切だと思っています。ただし、平等とはマジョリティと同じになるということではありません。私はラーメンが好きという面では健常者のラーメン好きの人と同じ人間です。しかし例えば点字を使うという違いもあるのです。平等を保障するだけでなく、違いを認めて「対等」に付き合うことこそが大切なのだと思います。
現代社会は、あまりにも視覚が優位な時代です。しかし、視覚にだけ頼っていると分からないこともあります。僕の役割は、そうした「目に見えない世界」の魅力を多くの人に伝えていくことだと考えています。これからも「さわる」ことをテーマにしたユニークな展示や、研究活動を続けていくつもりです。
(注1)琵琶の弾き語りを職業とした盲目の僧侶
(注2)盲目の巫女
(注3)三味線の弾き語りなどをして各地を巡る盲目の女芸人
インタビュー/林 勝一(東京都人権啓発センター 専門員)
編集/小松 亜子 撮影/細谷 聡
『目に見えない世界を歩く-「全盲」のフィールドワーク』(平凡社新書、2017年)

Copyright © Tokyo Metropolitan Human Rights Promotion Center. All rights reserved.




