本文
人権とスポーツ2020 人権の視点から見れば、オリンピック・パラリンピックはもっと感動する
TOKYO人権 第71号(2016年8月31日発行)
特集
人権とスポーツ2020 人権の視点から見れば、オリンピック・パラリンピックはもっと感動する
2020年の東京大会に向け、本誌はオリンピック・パラリンピックを人権の視点から見つめる連載を始めます。第1回となる今回は、オリンピックの根幹にある人権尊重の理念について、首都大学東京特任教授の舛本直文(ますもとなおふみ)さんにお話をうかがいました。
オリンピック憲章が謳う人権の尊重

舛本直文さん
オリンピック・パラリンピックは、4年に1度のスポーツの祭典として、多くの人が選手のメダル争いに注目します。しかし、オリンピックはもともと、スポーツを通した教育や平和のために誕生した祭典で、人権と深い関わりがあるのです。
「近代オリンピックの父」と呼ばれるフランスの教育家、ピエール・ド・クーベルタン男爵は、スポーツは体を鍛えるだけでなく、心身の調和のとれた人間を育成し、フェアプレーの精神や友情、道徳、連帯感を育むことができると考えました。さらに、国際的な競技会で他国の選手と親しくなり、多様な文化や芸術に触れることで、平和な社会の実現につながると考えたクーベルタンはオリンピックのあるべき姿として、「オリンピズム(オリンピック精神)」を提唱しました。そして、1894年に国際オリンピック委員会(IOC)が設立され、古代ギリシャでおこなわれていたオリンピックは復興されました。
十九世紀末、ヨーロッパ列強による植民地争奪と勢力圏拡大が激しさを増していた時代に復興されたオリンピックは、こうしたクーベルタンの教育と平和の思想に基づいているのです。そして、1908年にはIOCにより「オリンピック憲章」が制定され、その後に定められた根本原則には、「人権の尊重」が謳われています。
オリンピック研究やスポーツ哲学が専門の首都大学東京特任教授、舛本直文さんは次のようにいいます。「人が平和に生きるには、人権が満たされていなければなりません。平和をめざすオリンピックの根幹に人権が位置づけられているのは理にかなったことです」。しかし、このような志を掲げながらも、オリンピックはさまざまな人権問題を抱えてきました。
オリンピズムの根本原則(抜粋)
- 2. オリンピズムの目的は、人間の尊厳の保持に重きを置く平和な社会を奨励することを目指し、スポーツを人類の調和の取れた発展に役立てることにある。
- 4. スポーツをすることは人権の1つである。すべての個人はいかなる種類の差別も受けることなく、オリンピック精神に基づき、スポーツをする機会を与えられなければならない。オリンピック精神においては友情、連帯、フェアプレーの精神とともに相互理解が求められる。
- 6. このオリンピック憲章の定める権利および自由は人種、肌の色、性別、性的指向、言語、宗教、政治的またはその他の意見、国あるいは社会のルーツ、財産、出自やその他の身分などの理由による、いかなる種類の差別も受けることなく、確実に享受されなければならない。
(日本オリンピック委員会「オリンピック憲章」2015年版・英和対訳より)
オリンピックが直面してきた様々な人権問題
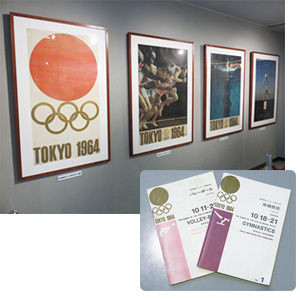
東京オリンピックメモリアルギャラリー(世田谷区駒沢公園1-1)には1964 年大会を中心に様々な資料が展示されている。当時の競技プログラムにはピクトグラムがデザインされている。
オリンピックの人権問題として、第一に、「女性の参加」と「性的少数者」の問題が挙げられます。
舛本さんは「1896年の第1回アテネ大会では、女性は参加できませんでした」といいます。当時の大会は、絶対神ゼウスを崇めるためにおこなわれていた祭典競技「古代オリンピック」をモデルにしており、これが女人禁制だったためです。「まだ女性の権利が十分に保障されていない時代だったこともあり、クーベルタン自身も女性の参加には反対していました」(舛本さん)。
1900年の第2回パリ大会からは、女性も参加するようになり、時代とともにその競技数も増えていきます。ところが、1964年の東京大会で、“男性のような”体格をした女子選手が陸上競技でメダルを獲得したことで、性別を疑う議論が起こりました。「その結果、1968年のメキシコ大会から、女性だけ性別検査が始まりました。これが女性の人権侵害にあたると多くの抗議がされますが、1999年に中止されるまで30年以上、女性のみの検査が続きました」(舛本さん)。
また、2014年のソチ冬季大会では、開催国のロシアにおける性的少数者に対する差別が問題となりましたが、IOCは、2014年末にオリンピズムの根本原則を改訂し、第6項に“性的指向による差別禁止”を加えました。「単に性的指向の単語を追加するのではなく、第6項全文が世界人権宣言の条文に近い文章になった点で、IOCが人権尊重という課題に力を入れていることがうかがえます」(舛本さん)。
人種差別との闘い
さらに、人種差別問題も、オリンピックに大きな影響を及ぼしてきました。例えば、アパルトヘイト(有色人種の隔離政策)をおこなっていた南アフリカ共和国は、1964年の東京大会以降、参加が認められず、1971年にはオリンピックから追放されます。復帰したのは、1991年にアパルトヘイトを撤廃した翌年のバルセロナ大会からでした。
また、1968年のメキシコ大会の陸上男子200mで、金メダルと銅メダルを獲得したアメリカ国籍の黒人選手が、表彰台でアメリカ国旗から顔を背け、黒い手袋をはめた拳を高く突き上げました。黒人差別に抗議する“ブラックパワー・サリュート”と呼ばれるこの行為は大きな物議を醸しました。オリンピック憲章では、競技会場などでの政治的パフォーマンスを許可していません。2人の選手は直ちに選手村を追放されました。ところが、実はこのとき、銀メダルを獲得して同じ表彰台に上ったオーストラリアの白人選手も、人権侵害に反対する白いバッジをつけていたのです。「スポーツ界では、白人選手の間でも人種差別に反対する動きがあったのです」(舛本さん)。
障害者のスポーツ参加とパラリンピックの発展
パラリンピックは、戦争で脊髄を損傷した兵士のリハビリとして、イギリスのストークマンデビル病院でおこなわれた車いすアーチェリー大会が基になっています。1960年のローマ大会開催後に、初めてパラリンピックが開催され、車いす選手によるアーチェリーや卓球など8競技がおこなわれました。車いす選手以外の障害者選手がパラリンピックに参加するようになったのは、1964年の東京大会からです。「東京大会は、より多くの障害者にスポーツへの道を開いたといえるでしょう」と舛本さんは語ります。
また、舛本さんは、近年のパラリンピックでは2014年のソチ冬季大会が印象に残っているといいます。「選手村に、国連障害者権利条約に賛同する人がサインすることができるボードが設置されました。東京は2度目のパラリンピックを開催する初めての都市でもあるので、こうした有意義な取り組みを積極的に取り入れた方が良いと思います」。
大会を通して人権のレガシーを残すために

1964年東京パラリンピック大会ポスター
(東京都人権プラザ「みんなのスポーツ展」より)
オリンピック憲章は大会開催地にレガシー(遺産)を残すことを目標としています。舛本さんは、1964年東京大会のレガシーの一つに「ピクトグラム(図記号)」を挙げます。「競技だけでなく施設や設備にもピクトグラムが体系的につくられたのは、東京大会が初めてでした。多様な国の人たちがピクトグラムで情報を理解する、言語のバリアフリー化に貢献したのです」。
オリンピックはさまざまな人権問題に直面してきましたが、2020年東京大会を通して私たちはどのような人権尊重のレガシーを残すことができるでしょうか。東京大会のエンブレムには「 みんなの輝き、つなげていこう。Unity in Diversity」という広報メッセージが添えられます。舛本さんは「一人ひとりの多様性を意味するDiversityという言葉は、人権啓発において大変重要」と指摘します。「オリンピック・パラリンピックを通して平和や国際交流、異文化理解などが深まり、多様性を尊重する人権感覚が育つことに期待したいですね」(舛本さん)。
これから私たちも、オリンピック・パラリンピックの話題を人権の観点からも見ることで、より深い理解や感動が得られるのではないでしょうか。
インタビュー/林 勝一(東京都人権啓発センター 専門員)
編集/小松 亜子
「多様性と調和」の実現を目指して

編集・発行:東京都総務局人権部
(注)「じんけんのとびら」ホームページにPDFを掲載しています。
東京都総務局人権部<外部リンク>
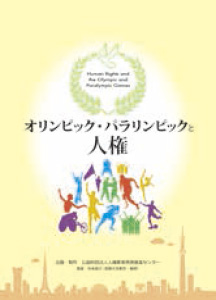
『オリンピック・パラリンピックと人権』
企画・製作:(公財)人権教育啓発推進センター
Copyright © Tokyo Metropolitan Human Rights Promotion Center. All rights reserved.




