本文
夜間学級の現在 ─期待される「誰もが等しく学ぶ場」としての役割
TOKYO人権 第107号(2025年8月31日発行)
特集
かつては戦後の混乱期に、昼間働く若者たちが学ぶ場として設置された中学校の夜間学級(いわゆる夜間中学)。現在では、学び直しの場として全国的にその役割が再評価されています。不登校の方や外国出身の方など、さまざまな事情で義務教育を十分に受けられなかった人たちが、あらためて学びに向き合う場となっています。こうした変化の背景や、現場で語られる声を通して、夜間学級の今を見つめてみました。
「義務教育相当の学び」をすべての人に
文部科学省は、2027年までに、全国すべての都道府県・指定都市に少なくとも1校以上の夜間学級を設置する方針を掲げています※。背景には、2016年に成立した「教育機会確保法」があります。形式的に中学校を卒業した不登校経験者や、日本で教育を受けてこなかった外国出身者など、学び直しを求めて夜間学級に通う人が増えています。
東京都に8校ある夜間学級の一つ、「足立区立第四中学校夜間学級」も、そうした変化の中にあります。同校の副校長・池田卓哉(いけだたくや)さんは、夜間学級の役割について「義務教育相当の教育を、すべての人に提供すること」と話します。同校には、日本で高校進学を希望する外国出身の若者、学ぶ機会が十分に得られなかった人など、多様な背景を持つ10代から70代の約40人が九つのクラスに分かれて学んでいます。
かつては、一度中学を卒業すると再入学が認められない制度でしたが、現在は見直され、形式的に卒業した人にとっても夜間学級が進路の選択肢として開かれています。池田さんは、「焦らず、自分のペースで学び直せる場所があるということは、生徒たちにとって大きな意味を持つ」と話します。

生徒の使用言語を自動翻訳しながら、少人数で授業を行う様子
一人ひとりに応じた学びを支える
夜間学級では、生徒の日本語力や教科ごとの理解度に応じて、柔軟な学びの場が用意されています。足立区立第四中学校の夜間学級では、国語や数学などの教科を学ぶ「一般学級」と、日本語習得に重点を置く「日本語学級」に分かれて指導を行います。特に日本語学級では、ひらがなの読み書きから始める生徒もおり、教科学習に進むまでに時間を要することもあります。池田さんは「それぞれの力に合った学びの形をつくることこそが、本来の教育ではないでしょうか」と語ります。
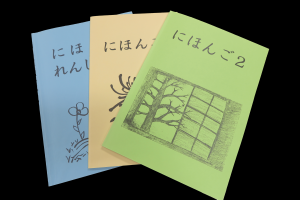
教室は「自分らしくいられる」場所
さらに、夜間学級は、生徒が安心して過ごせる居場所としての役割も果たしています。池田さんは、同校の夜間学級入級以前に不登校を経験していた10代の生徒が、多様な国籍や年齢の仲間と過ごす中で、周囲とコミュニケーションが取れるようになった事例を紹介し、「ここで学び直し、人と関わる力を取り戻していく。生徒たちが『自分でいていい』と思えることが何より大切だと感じています」。
夜間学級は今、全国であらためて注目されています。年齢や国籍を問わず、誰もが等しく学ぶ権利を保障するための場所として、「もう一度学びたい」という思いに応える場所として、夜間学級はこれからも大切な学びの場となっていきそうです。

池田 卓哉さん
インタビュー・執筆 吉田 加奈子(東京都人権啓発センター 専門員)
※ 文部科学省は、教育機会確保法等に基づき、すべての都道府県・指定都市に少なくとも一つの夜間中学が設置されるよう促進を行なっている。2025年4月時点で41都道府県・指定都市合わせて62校設置済み。2026年に5県で設置予定のほか、2027年度以降も新設等を検討する動きがある。
Copyright © Tokyo Metropolitan Human Rights Promotion Center. All rights reserved.




