本文
社会から見えない存在にされる 人々の声を表現したい
TOKYO人権 第104号(2024年12月31日発行)
インタビュー
Profile

ヒオカ(ひおか)さん
ライター。1995年生まれ。noteで公開した「私が“普通”と違った50のこと―貧困とは、選択肢が持てないということ」が話題を呼び、ライターの道へ。“無いものにされる痛みに想像力を”をモットーに、弱者の声を可視化するための取材・執筆活動を行う。「婦人公論jp」「ミモレ」「ダイヤモンドオンライン」「ビジネスインサイダー」「現代ビジネス」への寄稿など、各種WEB媒体で活躍中。著書に『死にそうだけど生きてます』『死ねない理由』がある。

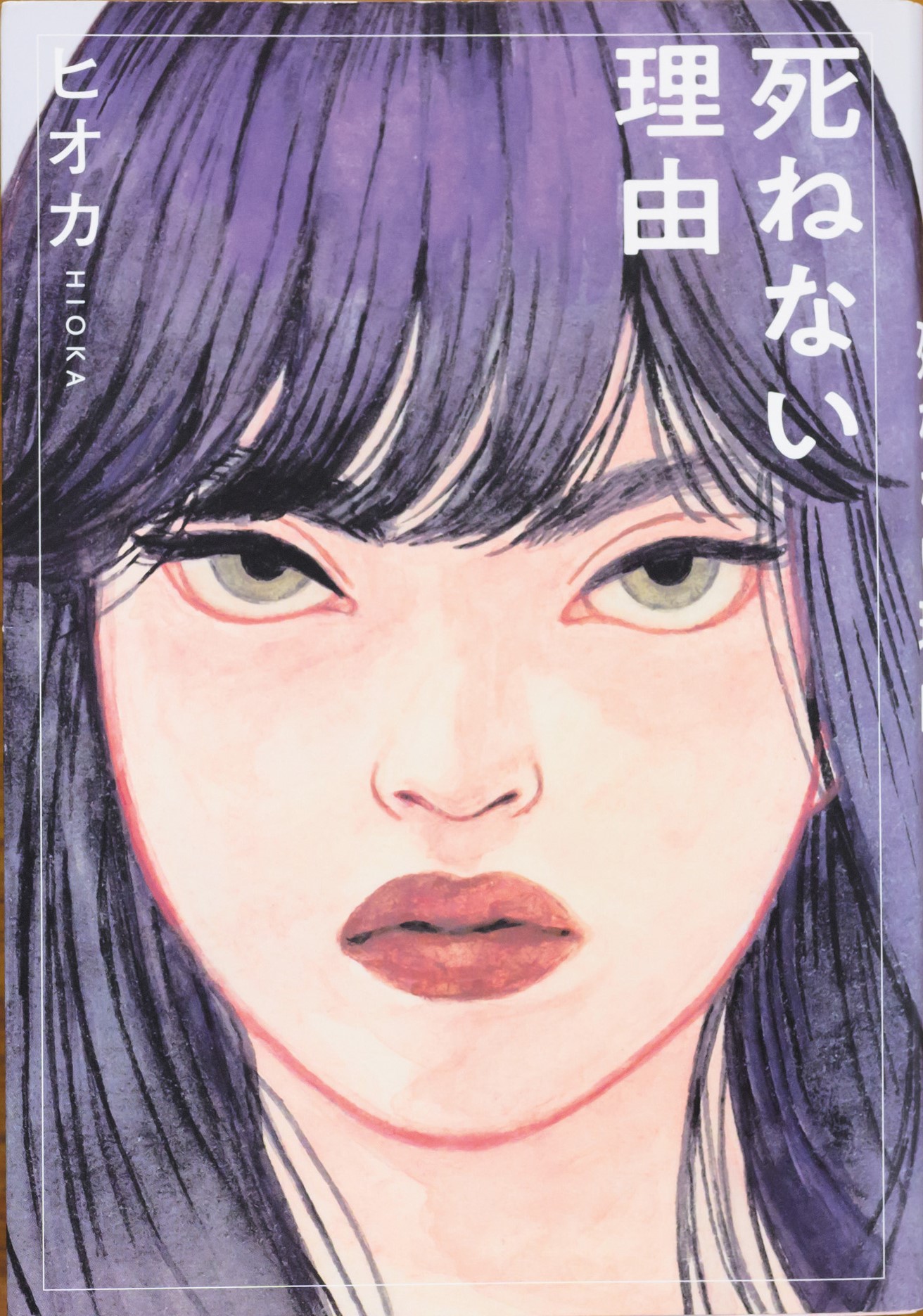
『死にそうだけど生きてます』 『死ねない理由』
(CCC メディアハウス) (中央公論新社)
絶望や苦悩の経験も、言葉にすることで人を救える力になる

習い事も、部活にも参加できない 実感した不平等
子どものころ、経済的に困窮していたことで、周囲の子どもたちとは違う教育環境で育っていたと思います。例えば音楽や体育など、学校で基礎的なことを学んで興味を持ち、さらにその先を学びたいと思っても、ピアノ教室や水泳教室には、私は通うことはできません。一方で周りの子どもたちは、おめかしをしてピアノの発表会に出演していたり、放課後に様々なクラブ活動をしていました。
教育機会は平等だといわれますが、自分の境遇は周りの子たちとはまるで違うのだということに否応なく気づかされました。それが本当に悔しく、子どもながらに胸がキリキリしました。勉強は好きでしたが、もちろん学習塾にも行けず、通信教育も受けさせてもらえません。やりたいと思ったことに挑戦できない。それが何より悔しかったのを憶えています。
中学高校では部活動への入部が必須でした。高校ではお金のかからないE.S.S.※1に入っていました。運動部ではユニフォームが必要だったり、移動費や合宿代がかかったりします。文化部でも道具を揃えなければならなかったり、なにかとお金が必要になるので活動するのが難しいのです。
そんな状況で、何かに興味を持っても、それ以上挑戦する機会を得ることはできませんでした。だから、自分は本当は何が好きなのか、何がやりたいのか、それを見つけることができませんでした。
家庭も落ち着いて勉強などできる環境ではありませんでした。家の中は散らかっていて、エアコンもなく暑さでぐったりしていました。そんな状況で、家にいると、何もやる気が起きませんでした。
弁論大会で、私の言葉がエネルギーとして聴衆に届いた
中学生のとき、いじめのターゲットにされました。そのころから、私の唯一の居場所は市立図書館でした。遠距離の中学校に通っていたため、放課後、母が迎えにくるまでの時間を、市立図書館で勉強したり本を読んだりして過ごしました。そこで出合ったいくつもの本が、今息苦しさを感じているこの環境ではない、もっと広い世界があるのだと教えてくれたように思います。
中学3年のとき、私の作文が校内で選ばれ、学校の先生に背中を押され弁論大会に出場しました。舞台に上がり聴衆を見据えたとき、体の奥底から力がたぎるのを感じました。そこでそれまで抑え続けてきた感情を爆発させました。自分の発した言葉が、聴衆にエネルギーとして届くのをありありと感じました。言葉で表現することの持つ力や喜びを、初めて体験した出来事でした。
担任の先生の勧めで志望校を決め、必死で勉強して、高校は進学校に進みました。それからも、市立図書館で勉強と読書を続け、難関大学への進学を志すようになりました。広い世界に出て行って、見たことのない景色を観たいという思いと、今の苦しい境遇から抜け出したいという願いがその動機でした。
もちろん塾に通うことはできず、家には勉強ができる環境はありません。図書館にある受験の情報誌や体験記を夢中で読み込んで、勉強法を模索しました。お年玉ももらっていない状況で、欲しい参考書も新品のものは買えず、インターネットで探して1円で売りに出されていたものを入手しました。勉強している時間だけが現実を忘れられたので、図書館で猛勉強に明け暮れました。難関大学ではありませんが、大学に現役で合格することができました。
豊かな暮らしと困窮する人 その間に見えたギャップ

子どものころ育った環境では、周りの人は皆、高卒で働いていて、大学に進学する人は一人もいませんでした。大学に進学したとき、国公立大学だから苦学生が多いだろうと思っていたのですが、実際はそうではありませんでした。周りの学生は皆ある程度裕福で、両親共に大卒です。本人もあらゆる教育を受けて育って、貧しい家庭環境など、存在すら知らないような人ばかりでした。
入学したときにパソコンを持っていなかったのも、電子辞書ではなく紙の辞書を使っていたのも私だけで、哀れむというより珍しがられました。何かにつけて社会の中での階層※2が違うと、常識や習慣、文化も全く違うのだということをまざまざと思い知らされ、本当に驚きました。
大学を卒業してライターとして出版業界と関わるようになってからも、そのギャップへの驚きは続きます。新聞社や出版社の社員は皆エリートで、子どもに習い事や私立受験、留学をさせるのは当たり前という世界です。
彼らには、塾や習い事をするという選択肢すらなく、衣食住にも困るような人々のことは、知識として知っていたとしても意識の中にはないように感じました。
派遣社員として働いていたとき、コロナ禍の影響で雇い止めにあったことがあります。翌日から来なくていいと突然契約を切られても、その後の保障は何もありません。急に収入の目途が立たなくなりました。社会保障の制度からは、短期の派遣で働く人たちの存在は想定されていないように感じました。
格差が広がっているといわれますが、社会に生きる人々が属している階層は、地層のように重なっているように見えます。同じ時代を生きていても、それぞれの階層は他の階層と交わらないことも多いのです。そして経済的に恵まれない階層は、その存在が社会から「不可視化」されているのではないかとさえ思えます。
ライターとして、他の階層の人たちと仕事をするようになってから、ここまで世界が違うのかと、まるで外国に来たような感覚を味わうようになりました。
クリスマスプレゼントやお中元・お歳暮を贈り合ったり、ホームパーティーを開いたりする豊かさのある文化。その文化圏の中で、親や周りの人から、テーブルマナー、金融リテラシー、医療制度、法律などの知識を、自然に学んできた人たちが、そこにいました。経済面に恵まれ、さらにさまざまな面からサポートしてもらえる人的資源にも恵まれた環境にいるのです。しかし、生まれ持ったアドバンテージを自覚することはとても難しいことです。リテラシーや自らの立場を、自らの努力で獲得したと思い込んでしまうこともあるのではないでしょうか。だから、貧困に陥った人々を「努力不足」「自己責任」とあたかも切り捨てるような発言をする人がいるのだと思います。
私は、環境に恵まれず透明な存在にされてしまっている、社会の端に捨て置かれたような人々の声を表現することで、その存在やそこから見える景色を可視化したいと思っています。
好きなものを持ち自分を生き直していく
ライターになり東京で暮らし始めると、貴重な体験をするようになりました。地元では貧困家庭で育ったことで、侮蔑的な目で見られたり、いじめを受けたりと差別されることもありました。ところが、東京では、そのバックグラウンドが、むしろ強みだと捉えられることがありました。バックグラウンドを話すと、「なにそれ、めっちゃロックだね」と反応されたことがあります。
あるお笑いタレントさんは、「今日取材に来てくれたライターさんは、すごくパンチが効いた育ちの人で…」とSNSでつぶやいて、悲惨とか、壮絶とかではなく、「パンチがある」と表現されたことがすごく新鮮だったことを覚えています。
そうしたことが何度かあったおかげで、自分の育ちを隠したり後ろめたく思ったりする必要はないのだと思えるようになりました。
過去を肯定してくれる人たちと出会ったことで、経済的に困窮していた過去があっても、自分に制約をかけなくてもいいのだと思えるようになりました。自分が望むことを追い求めていいのだと。例えば、一見、派手に見える服装やファッションを身につけることで、バッシングを受けることもあります。それでも、これまでは望んでも叶わなかった、好きなものを持つことや、身に着けることは、「自分の人生を生き直していく」ために必要なことだと考えています。生きていくことだけで精いっぱいで、得ることのできなかった文化や豊かさを取り戻していきたいし、今までできなかった自分を表現することを思い切りやってみたいのです。
経済的に困窮している人が夢や理想を語ると、「もっと現実を見るべきだ」と批判されることがあります。しかし、貧しいことを理由に夢をあきらめることを強いられたり、職業や好きなものから遠ざけられたりすることは、本来誰もが持つ人権が制限された状態を受け入れることに他ならないと思います。




同じように苦しんでいる人を救う言葉を紡ぎ届けたい
伝えることで「自分だけじゃない」を届けたい
これまでの私は、いつどうなるかわからない不安な状況の中で、ただ生きていくことに必死でした。学生時代から数年前まで、家賃を節約するために格安のシェアハウスを転々としていました。シェアハウスには、エアコンがなく過酷な暑さで、何度も熱中症になりました。ほかにも、雨漏りで床に水たまりができたり、カビやハウスダストでアレルギーを発症することになったりと、劣悪な環境のところばかりでした。
そんな住環境の中で、明日を生き延びるためのお金の心配をしなければならない。生きていくための不安が多すぎて、漠然と「生きていけない」と思っていました。常に不安にさらされて、生存本能が搾りとられて生きようとする気力がなくなっていきました。
今は一人暮らしができるようになり、お笑いタレントやアーティストなどの大好きな「推し」ができました。好きな音楽やファッションなど、文化的なものを楽しむ余裕ができたことで、初めて「生きてもいいのかな」と思えるようになってきました。
好きなお笑いタレントが語る貧しかった子どものころの経験が、私の子どものころの体験に重なりました。その人が体験した絶望やどうしようもない苦しさが、言葉になって紡がれ、その一つひとつに共感し、救われる気持ちになりました。
この苦悩は自分だけじゃない、そう思うことで救われることがあります。私も自分の苦しかった過去を言葉にすることで、誰かの心が少しでも楽になったらいいなと思っています。読んでくれた人が「貧しくても自由に生きていいんだ」「自分だけじゃない」と思ってくれれば、これまでの苦労も報われ、私も救われるのです。
経済的に苦しかったという私のバックグラウンドは、私を構成する数多くの要素のたった一つでしかありません。「貧困家庭出身」という立場からメッセージを届けてきたことは確かですが、いつまでも「そういう生い立ちのかわいそうな人」にとどまる必要はないと思っています。
そこから抜け出して、次のステップに進んでいきたいと考えています。これからは、音声など、文章以外の表現も模索していきたいと思っています。
インタビュー 吉田 加奈子(東京都人権啓発センター 専門員)
編集 杉浦 由佳
撮影(表紙・2 〜6ページ) 百代
ヒオカさんおすすめDVD
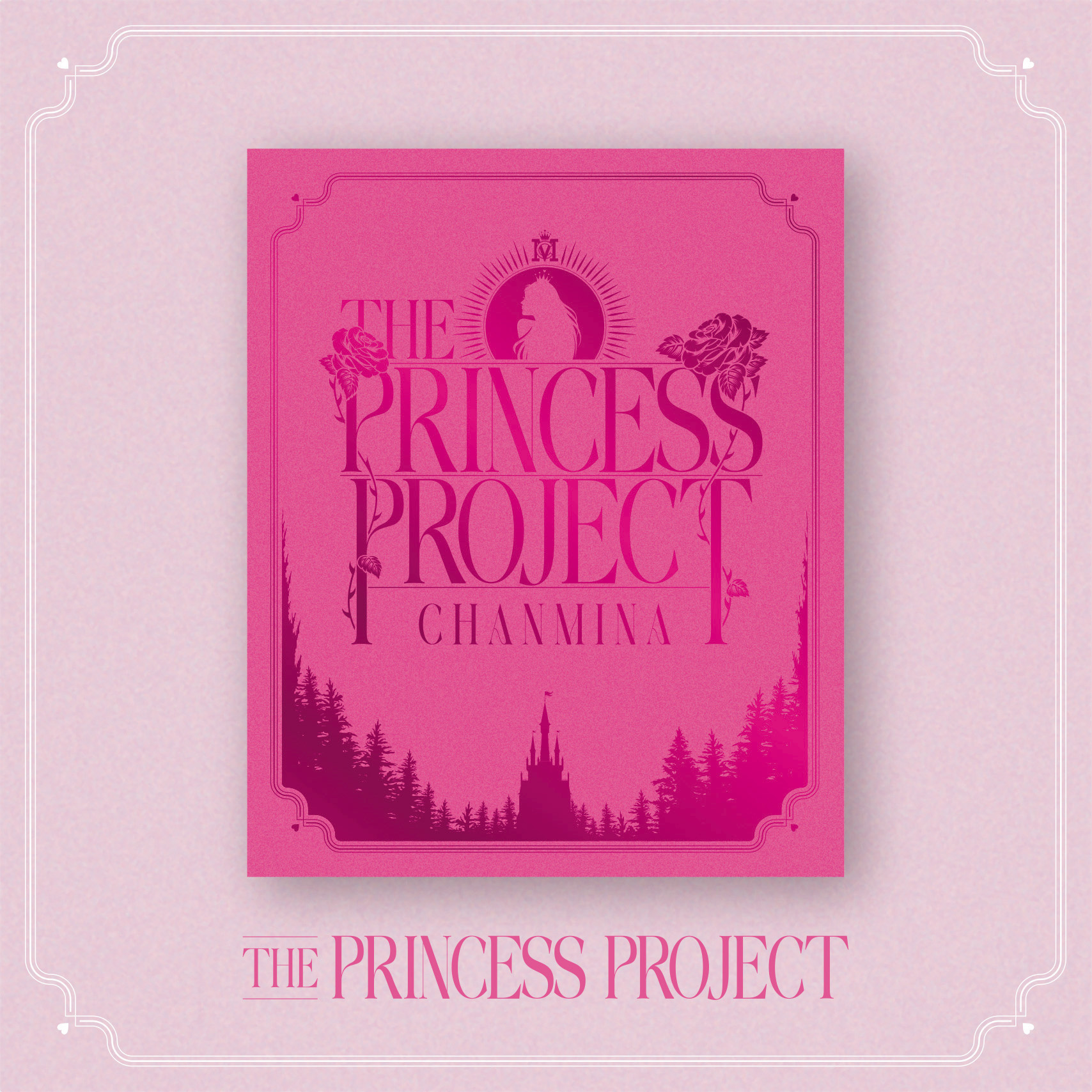
ちゃんみな
『THE PRINCESS PROJECT』
提供:ワーナーミュージック・ジャパン
※1 英語を使った活動に取り組む部活動。
※2 社会経済的地位によって序列化された社会層。財産・職業・学歴・年齢などが尺度とされる(岩波書店『広辞苑第7版』より)。
Copyright © Tokyo Metropolitan Human Rights Promotion Center. All rights reserved.




