本文
性暴力被害から生き延びて、当事者と研究者の間で生きる
TOKYO人権 第100号(2023年12月28日発行)
インタビュー
Profile

小松原 織香(こまつばら・おりか)さん
1982年兵庫県生まれ。大阪公立大学客員研究員。大阪府立大学大学院人間社会学研究科博士後期課程修了。博士(人間科学)。著書に『性暴力と修復的司法』(西尾学術賞受賞)、『当事者は嘘をつく』。戦争、犯罪、災害などのサバイバー(生存者)のその後を研究対象とするほか、修復的正義の研究を行なっている。

『当事者は嘘をつく』(筑摩書房)
仲間との出会いを通して社会の問題に気づいていった
「私はあなた(加害者)と話したい」 当事者としての願い

私は19歳の時に性暴力に遭いました。そのことにより、子どもの頃から培ったアイデンティティは破壊され、全く別の人生が始まりました。被害を生き延びた人たちのことを「サバイバー(生存者)」と呼びます。たくさんのものを失ったけれど、私は今も生きているし、元気に暮らしています。おそらく、見た目では分かりません。
若い頃は、精神科医やカウンセラーの言葉にいつもがっかりしていました。かれらは、私を「ものが考えられない哀れな人間」として扱い、対等に話をすることはありませんでした。
たしかに当時の私は打ちのめされていました。つらい記憶がよみがえり、苦しみのあまり「死ぬしかない」とも思いました。でも、私は自分の意思をはっきりと持っていました。加害者に謝ってほしかったし、対話をしたかったのです。
残念ながら、当時の性暴力の被害者支援では、加害者は危険であるから二度と会ってはいけないと考える人がほとんどでした。もし、本当のことを言えば「あの人は回復していない」「加害者にとらわれている」とマイナスの見方をされました。だから、私も黙っていました。
私が変わったのは、自助グループに参加したのがきっかけです。レイプ、児童性虐待、上司からの性暴力、DV(親しい人からの暴力)、みんな違う形での被害を受けてきたけれど「誰にも言えなかった」ことは同じでした。全員が当事者だという空間で、初めて私は胸の奥深くに突き刺さった痛みを言葉にしていくことができました。私を救ってくれたのはサバイバーの仲間たちです。
サバイバーが集まれば、「加害者に会いたい」「謝ってほしい」という言葉がどんどん出てきます。そのとき、私は性暴力の被害者と加害者の対話の必要性を確信しました。専門家の言葉より、仲間の言葉を信じました。
自助グループの思い出はきれいな話だけではありません。傷ついた人間が寄り集まれば、喧嘩(けんか)も起きるし、お互いの被害の重さ比べ、嫉妬や攻撃も始まります。私はそういう醜い感情の全てを受け止めたかった。それくらい、当時は仲間への想いが熱かったからです。
かれらの言葉を聞くと、性暴力による心の傷以外の困難が見えてきます。多くの仲間たちは貧困や飲酒、薬物、借金、就労困難、障害、難病、精神疾患、カルト宗教、子育てや介護など、複雑な問題を抱えていました。一般的に言えることですが、社会的に弱い立場にある人は、災害や暴力に襲われた時、より深刻な被害を受けやすい。性暴力では、まさにこの構造の中で弱い立場にある人たちがシビアな状況にありました。
それを目の当たりにして、私は「死んでる場合じゃないぞ」と思いました。性暴力の問題を考えるには、社会構造を捉え、分析する必要がある。私は俄然(がぜん)、奮い立ちました。
「専門家の立場から反撃しよう」 闘うために大学院に進学
私は大学院への進学を決意し、修復的正義の研究を始めました。修復的正義とは、被害者と加害者の対話のプログラムを中心とした、紛争解決のアプローチです。近所の図書館の最新刊のコーナーに並んでいた法学雑誌を手に取ったところ、偶然、知ることになりました。その頃は法学になんて興味がなかったのに。運命だったのかもしれません。
その雑誌は修復的正義の特集をしていて、性暴力被害者の支援をしている精神科医が、性暴力の場合は被害者と加害者の対話は不可能だという調子で論考を書いていました。私は彼女に反論したいと思いましたが、相手は英語論文をもとに議論を進める専門家です。同じ土俵に立つにはこちらも勉強しなければなりません。「だったら、研究者になってやろう」と思って、大学院に進学しました。最初から闘うつもりでした。
それから10年近く、院試を受け、修士課程・博士課程に進み、論文を書く生活を続けました。2016年には性暴力事例における修復的正義の可能性を探究した博士論文を執筆し、翌年には出版しました。(『性暴力と修復的司法 対話の先にあるもの』成文堂、2017年)
「他人の痛みは分からない」ことから出発して他者と向き合う
水俣で出会った人たち 「当事者」の痛みはわからない

研究者になった私は、「水俣」に出会って、大きく方向転換をすることになりました。水俣では、1956年に水俣病患者が公式に確認されて以降、公害の問題が長く続いてきました。今も、地域に暮らす人々の間には水俣病をめぐって深い分断があります。その中で、他の地域から水俣に移り住み、被害者の支援を続ける人たちに私は出会いました。
それまで私にとって支援者とは、被害者を助けることを生業とした職業人でした。でも水俣では、どっぷりと地元に浸かって、人生の全てが水俣病に繋がるような生き方をしている支援者がいくらでもいます。その良し悪しはともかく、「どこから支援者と当事者の線引きをしようか」と私は悩み始めました。他方、かれらは未熟な研究者であった私を受け入れてくれるようでした。
同時に、私が困ったのは水俣病の被害を受けた当事者の苦しみが全く分からなかったことです。もちろん、学べば学ぶほど被害の深刻さは理解できますし、当事者の言葉をじっと聞けば胸が痛み、言葉を失うほど衝撃を受けます。しかし、どんなに共感しようと努めてみても、自分が性暴力の被害で苦しんだ、当事者としての痛みの激烈さとは、比べものにならないのです。「やっぱり当事者の痛みは伝わらないものなんだな」と納得するしかありませんでした。
水俣で出会った支援者と「当事者の痛みは分からない」ことを前提としながらも「第三者がこの地でできることはあるのか」について何度も話しました。今も私の中で明確な答えはありません。それでも水俣を訪れ、自分の鈍感さに直面しながら、当事者の言葉を聞き続けています。
なぜ「支援者」になるのか 「嬉しく思えない」という話
世の中では社会的に弱い立場にある人の支援者は善人だとされていますよね。でも、私は変だと思っています。どうして見ず知らずの人を助ける職業に就きたいのかを考えると、 その動機は何なのか気になります。
通常であれば、私たちは個人として人と出会い、相手の持つ弱みに気づきます。ときには差別されてきた経験を知り、その人の力になりたいと思うでしょう。それは自然で美しい行為です。
支援者になりたがる人は、最初からラベルのついた弱者に自分から近寄っていくようなものです。でも、よく考えてみると、ひとりの人間のごく一部だけをクローズアップして、そこだけを見ようとする欲望は奇妙に思えます。
正直にいうと、私は自分に対して「性暴力被害者だから」という理由で近寄ってくる人は嫌いです。相手は私が物珍しいのかもしれない。知りたい情報があるのかもしれない。その人の過去に何かあったのかもしれない。でも、私は性暴力被害者である前にひとりの人間です。「私はあなたが学ぶための素材ではない」と伝えたいです。
当事者としてカミングアウトすることは、一方的に属性のラベルを貼られることを受け入れ、教育材料にされることを引き受けることでもあります。でも、いつだって気分は悪いし、「嫌だな」と思っています。そのことは念頭に置いていてほしいです。
「支援者になりたい」というのも同じことです。当事者は支援されるために存在しているわけではありません。私は性暴力について学ぶための講座では、いつも「『相手を助けたい』という欲望をコントロールしましょう」と伝えています。「救世主になりたい」という願望を抑えて、相手の言葉を黙って聞く。そうすることが良い支援の第一歩です。主役は支援者ではなく当事者ですから。
他人を助けたがる人は、もしかすると「本当は自分が救われたい」とか、「救われなかった過去の自分を救いたい」という思いがあるのかもしれません。あるいは、相手の痛みと自分の痛みを重ねて、分かり合った気分になっているだけという可能性もあります。
私自身、水俣病の被害を受けた人たちに、同じことをしています。研究者という第三者の立場でありながら、勝手に当事者に自己同一化して、水俣という場から離れられなくなっているのです。人がそういう巻き込まれ方をすることを、私自身もよく分かっています。ただ、それは美しくも善くもない行為です。その出発点は自覚する必要があると思います。

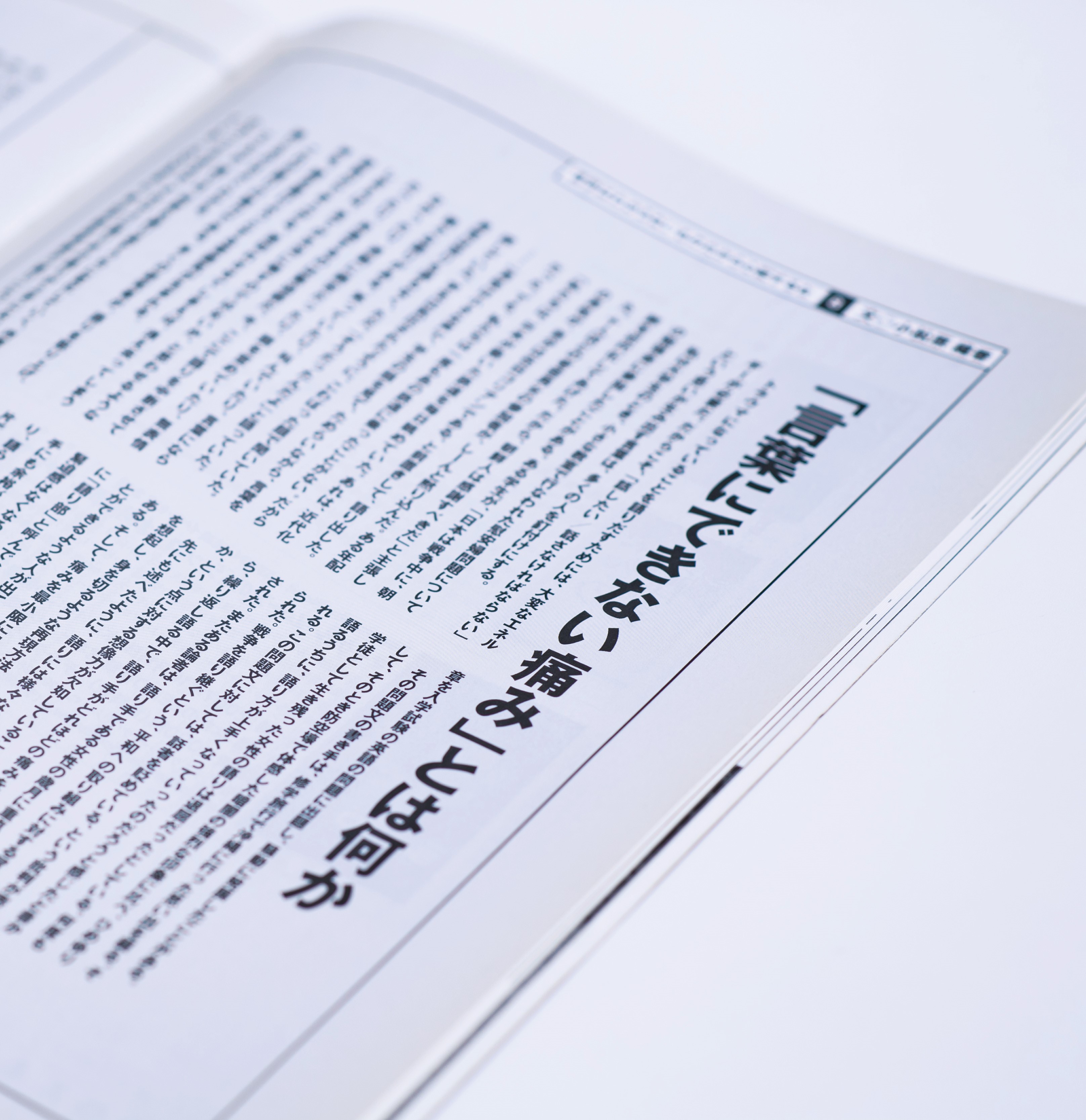


性暴力の報道についてと 大切にされる価値について
性暴力についての報道に、世間の人たちが関心を向けることは良いことだと思います。でも、私はそういう話題が出ると、その場を離れて会話に加わらないようにします。
私が具体的な事件について自分の考えを述べるのは、直接、被害者や加害者に関わったときだけです。よく講座でも「この事件についてコメントしてください」と言われますが、原則としてお断りしています。流行の話題として消費したくありませんし、報道には出てこない、深くて立ち入れない世界があるはずだからです。
報道ではセンセーショナルに、権力者による激しい性暴力が報じられますね。でも、実際にはもっと地味で、「これは暴力だろうか」と被害者自身が戸惑うような、日々の暮らしの中の性暴力がたくさん起きています。
例えば、最近は男性の性暴力被害に注目が集まっています。特殊な場所でなくても、学校の教室で無理やり服を脱がされたり、触られたりした男の子たちはいます。「男同士の悪ふざけ」だと割り切って、心の痛みをかき消している人もいます。つらい体験に「性暴力」と名前をつけることは、救いにもなれば傷つきにもなります。無理に「正しいこと」をする必要はありません。
人権の話が嫌いな人もいると思います。「マイノリティは立ち上がらないといけないし、傷ついた人は回復しないといけない」というお説教をされるかもしれないと身構える人もいると思います。でも私は、「無理に回復しなくてもいいし、立ち上がらなくてもいい。誰かを助けなくていいし、理解しなくてもいい」と本気で考えています。
今、この文章を読んでいる方の中にも「生きていくのが大変だ」と感じている人がいるでしょう。そういうときは、生き延びるだけで十分ではないでしょうか。「あなたには大切にされる価値がある」ということが、人権があるということだと私は思うからです。
インタビュー 吉田 加奈子(東京都人権啓発センター 専門員)
編集 杉浦 由佳
撮影(表紙・2〜6ページ) 百代
小松原さんのおすすめ書籍
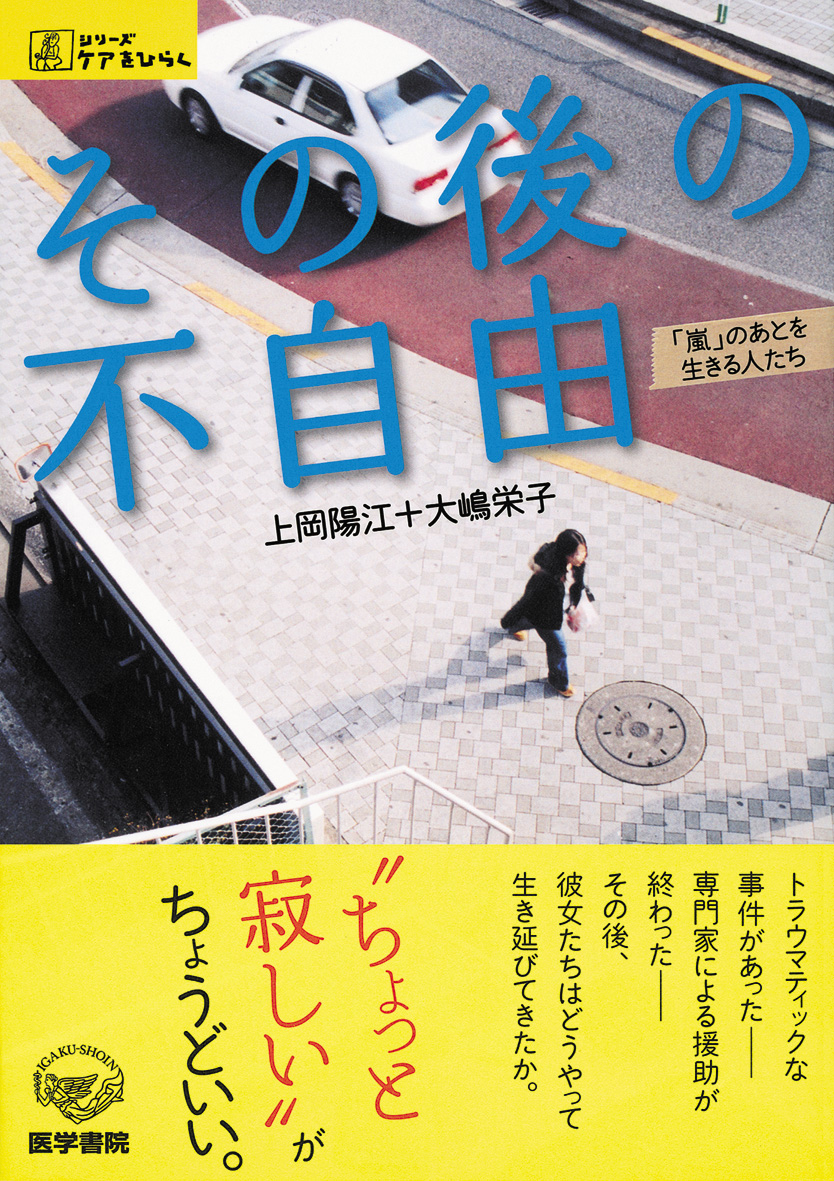
『その後の不自由
「嵐」のあとを生きる人たち』
上岡 陽江・ 大嶋 栄子 著(医学書院)
本人の加筆・修正による文章を掲載しています。このため、文章は個人的見解を含みます。(「TOKYO人権」編集部)
Copyright © Tokyo Metropolitan Human Rights Promotion Center. All rights reserved.




