本文
苦しみもがく自分の奥底に在る思いを五行詩に込める
TOKYO人権 第106号(2025年6月30日発行)
インタビュー
Profile

岩崎 航(いわさき・わたる)さん
詩人。1976年、仙台生まれ。本名は岩崎稔(みのる)。3歳頃に症状が現れ、翌年に進行性筋ジストロフィーと診断される。現在は胃ろうからの経管栄養と人工呼吸器を使用し仙台市内の自宅で暮らす。20代半ばから短詩に関心を持ち、2004年秋より五行歌形式での詩作をはじめ、2006年に『五行歌集 青の航』を自主制作。著書に、詩集『点滴ポール 生き抜くという旗印』、エッセイ集『日付の大きいカレンダー』、兄・健一との共著、画詩集『いのちの花、希望のうた』、第2詩集『震えたのは』(いずれもナナロク社)を刊行。
X(旧Twitter): iwasakiwataru

公式サイト
風にあたり陽(ひ)の光を浴びる。これも「生活」ですよね?
重い障害があっても当たり前の「生活」ができるよう介護業界の人手不足が解消されてほしいのです。

筋ジストロフィーが発症した頃のことについてお聞かせください
筋ジストロフィー※1は、全身のあらゆる筋肉を正常につくることができず、筋力が低下していく遺伝性疾患の総称です。
私の場合、3歳くらいで発症しているので、発症前後の記憶が定かではないのですが、幼少期は転びやすかったものの、普通に歩く、座る、立つことはできていました。私には7歳上の兄がいて、その兄が既に筋ジストロフィーを発症していたため、親が「もしや」と思って私を医療機関に連れて行き、私も兄と同じ病であると診断されたと聞いています。とは言え、私自身がこの病を正しく理解するのはずっと後のことで、幼少期に親から病について説明されたことはありません。ですから、子ども時代は「自分は足が悪いんだな」という理解でした。
親の方針もあって、小中学校は地域の公立学校に通っていました。階段は手すりを使ってよじ登る必要があったし、運動会ではいつも最下位でしたが、そういうことが「嫌だった」というよりは「肩身が狭い」という気持ちでしたね。同級生たちにとっても、私は「足の弱い少年」という認識だったのでしょう。良くも悪くも過剰に特別扱いをされることはなく、割と穏やかに、子どもらしい日々を送れていたように思います。
同じ病のお兄さまはどのような存在でしたか?
兄の様子を見てはいましたが、小学校の低学年のころは、それが自分に直結していなかったんです。成長とともに自分の体が思うように動かなくなっていく中で、徐々に「自分も兄と同じ病気なんだな」と理解を深めていく感じでした。
兄も地域の公立中学校に通っていたのですが、特徴的な歩き方で「やっと歩けている」状態だったために、苛(か)烈(れつ)ないじめに遭っていたようです。当時の私は幼すぎて、兄の苦しみに気づくことも、理解することもできていませんでした。その後まもなくして歩くことも立つこともできなくなった兄が、そのもどかしさを母にぶつけているのを見たことがあるんです。「もうこんな足なんかいらない!」と悲痛な声で訴える兄の姿を断片的に覚えているのですが、それに比べると、私は兄が通った道よりも少し楽な道を進めたように思います。もちろん私も歩けなくなる、立てなくなる、そういう現実を突きつけられたときはショックを受けましたが、私の場合は、もう一方で「これからは転ばずに済む」といった思いもあったんです。兄の姿を見ていたから、自分の中に鬱(うっ)積(せき)していくものを、自力で消化していく助けになったのかもしれません。
岩崎さんの暮らしに「今、必要なこと」とは?
今、私は24時間絶え間なく人工呼吸器をつけ、食事は胃ろうといってお腹に開けた小さな穴から、胃に直接チューブを通しています。ベッドの上で生活をしており、何をするにも介助が必要です。以前は両親の介助で暮らしていましたが、このままではいずれ限界が来ると思い、公的な介助を利用することにしました。両親が80歳近くになった2018年頃には毎日24時間ヘルパーさんの介助で暮らすようになりました。ただ、私の体は少しでも無理な動かしかたをすると筋肉を傷めてしまうので、介助の難易度が高いこともあり、介助体制の維持だけでも「綱渡り」に近い現状なんです。「もしヘルパーさんが欠員状態になったら」「もし代わりに入れるヘルパーさんがいなかったら」、そんなことを考え出すと追い詰められてしまいます。
「生活」には、「風にあたり陽(ひ)の光を浴びたいな」とか「気晴らしに散歩をしたいな」とか、そういうことも含まれますよね。けれど、今の私にはそんな願いもなかなか叶いません。外出時には寝台型の車いすを使用するのですが、介助には2人のヘルパーさんが必要となり、人員を確保するのがとても厳しい状況にあります。仮に、なんとか確保できても、外出の日が雨だったりすると、待ち望んでいた機会は流れてしまいます。「じゃあ、明日にしましょう」というわけにもいかず、また、いつになるかわからない「人員確保できる日」を待たなくてはなりません。
今の私に必要なものは「安心できる生活」です。つまり「安心できる24時間介助の体制」です。制度的には「24時間介護の支給量※2(外出時等の2人介護分を含む)」を行政に認めていただいているのですが、人手が不足していれば、その支給量をフルで受けることが難しいのです。人手不足の解消に向けて、自分でもできることをしようとSNSでヘルパーさんを募集しました。その甲斐あって、1人のヘルパーさんとつながることができましたが、24時間介助の体制が手薄な状況であることに変わりはありません。何かがすぐに変わるわけではないけれど、介助なしには生きられない自分の状況や思いを発信することは続けていきたいと思います。


青空のもと外出をする。
そんなささやかな日常を航さんは日々、
待ち望んでいる
第一詩集『点滴ポール』は大きな反響を呼びました。
五行詩を詠み始めたのは2004年、私が25歳の時です。学校に通っていた頃よりも、体がかなり不自由になり、行動範囲が狭くなり、その結果、人との関わりも激減していきました。あまりにも一人の時間が長すぎて、人と関わることに恐怖を感じるような時期もあったくらいです。けれど、自分がどんなに努力をしても変えられないことがあります。自力でも他力でもどうにもならない。そんな無力さを思い知らされると、自分はどう生きていくのかってことを、いやおうなしに考えさせられるわけです。ときに気持ちが倒れてうずくまる。その気持ちをまた「生きる」というほうへ必死に立て直し、立て続ける。そんなふうに葛藤し、苦しみもがく自分から洩(も)れ出てくる思いを言葉にしたものが五行詩です。
2013年に『点滴ポール 生き抜くという旗印』を上(じょう)梓(し)してからは、それを介して人との出会いや関わりが生まれ、その関わりの中で励まされることも増えました。自分の苦しみや悩みを腹を割って話せる人もできたし、生きたいと思わせてくれる大切な人に出会うこともできました。五行詩を書くことは、私が人と繋がって生きてゆくための営みになっているのだと思います。

青春時代と呼ぶには
あまりに
重すぎるけれど
漆黒とは
光を映す色のことだと
『点滴ポール』より
『点滴ポール 生き抜くという旗印』
写真:齋藤陽道、2013年、ナナロク社
岩崎さんの第一詩集。谷川俊太郎さんをはじめ多くの方から高い評価を得る。
未来に向けて思うことや望むことは?
法律や社会制度を変えることで、改善できる社会課題はたくさんあるのに、そういうことって遅々として進みませんよね。私に関して言えば、訪問介護や医療的ケアを受けることが生命に直結しているにも関わらず、介護業界の人手不足の状況は一向に変わりません。家族の有り無し、運や偶然に左右されずに、障害のある当事者が社会的な支えを得ながら「自分らしく」生きていける世の中になってほしいです。
50年前、100年前に比べれば、障害者の人権の状況は劇的に変わっています。障害者が見向きもされなかった時代から、様々な制度が整ってきました。先人たちが勝ち取ってきたものの恩恵を、私も受けながら生きているのは事実です。でも、まだ足りない部分がある。そう考えると、自分の困難を憂えずに済む時代にたどり着く前に、私もまた「生きて闘った人たちの層の一人」になるのかなと思うこともあります。
今、私は49歳です。医療環境が整うことで、この病気でも50歳を過ぎても健在の方がいます。せめて私が生きている間に、必要な手助けがあれば自分で人生を作っていける社会に変わる「兆し」だけでも見えてきてほしい。大切な人のために長く精一杯生きたい。できることなら、両親を見送りたい。そういう思いもあって「60歳まで生きる」と詩集『震えたのは』に記したのです。そうは言いながら、追い詰められてしまうこともしばしばで、その度になんとか踏ん張っているというのが本当のところです。
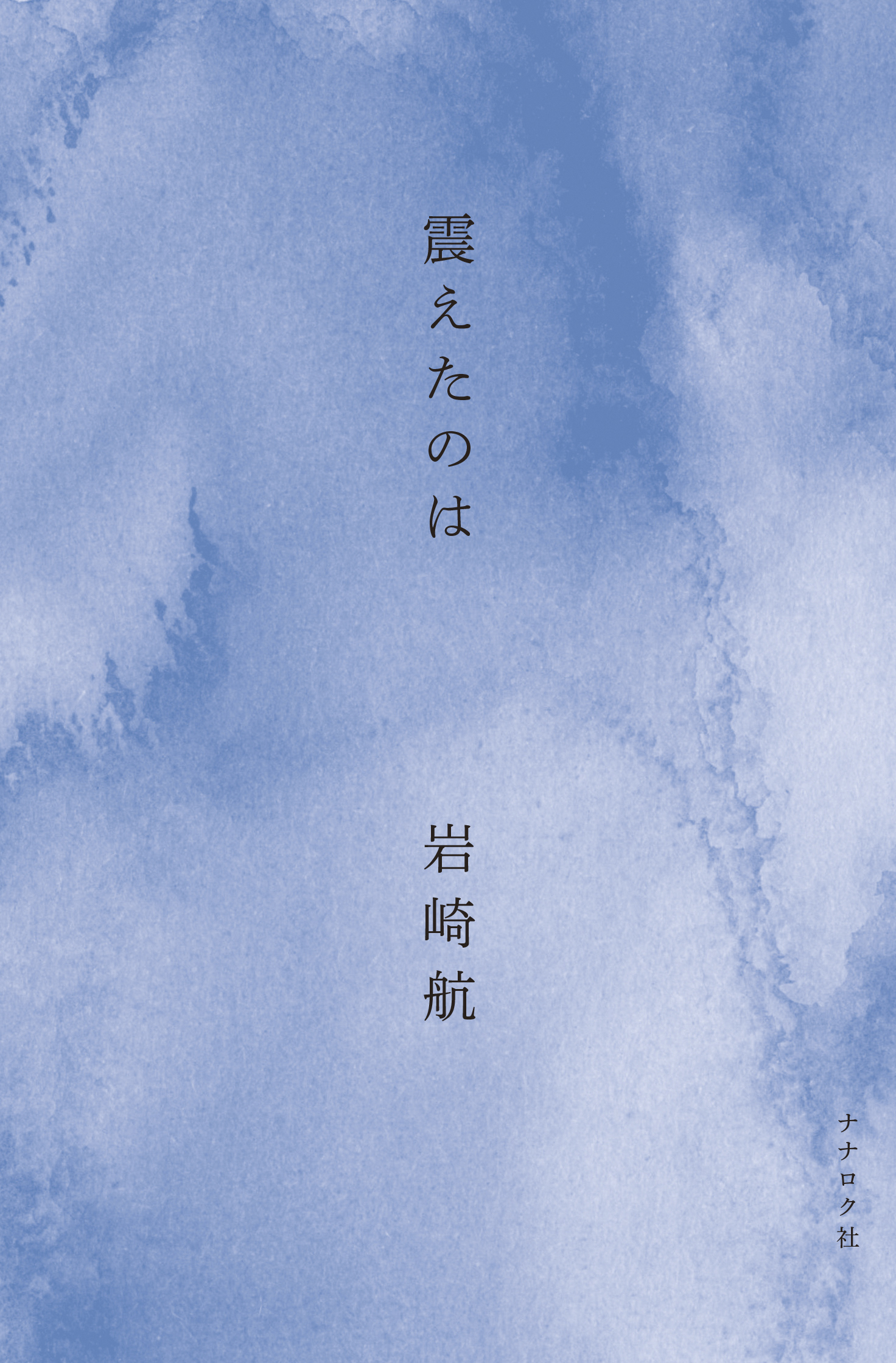
鼻マスクをつけ
蛇だ管かんをつけ
ほらほら
眺めてみると
小さなゾウさん
『震えたのは』より
『震えたのは』
挿画:岩崎健一、2021年、ナナロク社
岩崎さんの第二詩集。兄、健一さんの花の挿絵が配されている。
苦しみは一人で抱え込まずに誰かに話すといい。
共感してくれる人の存在は自分の生きる力になるから。
岩崎さんの「生きる」原動力はどこから?
苦しみに抗おうにも力が湧かず、自分一人で抱えこみ、否定的な想像に翻(ほん)弄(ろう)され、自分でも「ちょっとまずいな」っていうレベルまで落ち込んでしまうことは今でもよくあります。そういう時に、信頼できる誰かに自分の気持ちを聞いてもらうと楽になります。聞いてもらったところで、自分が直面している状況は何も変わらないのですが、少なくとも自分の苦しみを理解し、共感し、「一緒に何とかしよう」と同じ方向を向いてくれる人の存在は私の生きる力になる。そういう意味では、五行詩を読んでくださった方々からの感想も私の大きな力になっています。もし五行詩を書いていなかったら、私の世界は狭いままだったし、もしかすると今日まで生きられていないかもしれません。
介助や医療的ケアを受けながら「生かされている」という日々ではなく、自ら話し、自ら人に会い、自ら動くことで「生きている」感覚を得ることが、「生きる」力につながっていくのだと思います。
今、何かに悩んでいる人に伝えたいことはありますか?
私は絶望の淵に追い詰められたときに、自分の心の奥底から出てきた言葉で自分を支えることで、生きてこられたとも言えます。また、五行詩に共感してくださる方々の存在に救われてきました。だからといって、達観したようなことは一切なく、今だって、尽きることのない不安や苦しみで、もみくちゃになりながら生きています。人それぞれ悩みや葛藤があると思いますが、なんとか踏ん張って「自分の人生を全うする」という気持ちを持ち続けていただきたい。これは私自身への言葉でもあります。
私にとっての「幸せ」は、特別な出来事や特別な状況のことではなく、今日という一日を無事に過ごせることです。「つつがない一日」をつくり、積み重ねていくなかで、自分を前に進めていく気持ちが生まれていくものだと思います。けれど、つつがない一日を送ることができずに困っている人が社会にはたくさんいる。ですから、そういう人たちを支える仕事や役割を担っている人がもっと大切にされる世の中であってほしいと切に願います。


岩崎さんの兄で画家の健一さんが花の絵を描き、航さんが詩を添えた『いのちの花、希望のうた』(ナナロク社)もまた読む人に大きな感動をもたらしている。
インタビュー 林 勝一(東京都人権啓発センター 専門員)
編集 那須 桂
撮影(表紙・2 〜6ページ) 齋藤 陽道
※1 筋ジストロフィーがもたらす主な障害としては、運動機能障害(歩行が困難になる)、呼吸機能障害(息苦しさ、肺炎のリスクが高まる)、心機能障害(心不全や不整脈の発生リスクが高まる)、嚥下機能障害(唾液や食べ物を飲み込むことが困難になる)などがありますが、発症年齢や重症度には個人差があります。根本的治療法は現在のところありません。
※2 「支給量」とは介護サービスを受けるために必要な時間や回数を指すもので、支給量は利用者の障害支援区分や生活環境、介護の必要性を個別に勘案して決定される。
Copyright © Tokyo Metropolitan Human Rights Promotion Center. All rights reserved.



